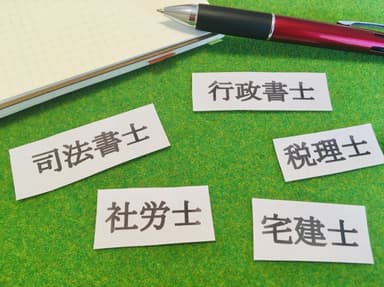特定財産承継遺言とは?特定遺贈との違いと作成時の注意点
公開日: 更新日:
はじめに
相続に関する法律知識を調べているとき、「特定財産承継遺言(とくていざいさんしょうけいいごん)」という言葉に出会う方も多いのではないでしょうか。この遺言形式は、不動産や預貯金、有価証券など、個別の財産を特定の相続人に承継させたい場合に活用されるもので、相続の場面において極めて重要な意味を持ちます。
一方で、「特定遺贈(とくていいぞう)」という似たような法的概念も存在し、両者の違いが分かりにくいという声もよく耳にします。実際、これらは使われる文言や相続人・受遺者の範囲、法的効力、手続きの簡易性などの面で大きく異なります。また、遺言書の文言を誤るだけで、意図しない結果を招いてしまう恐れもあるため、正確な知識が求められます。
本記事では、「特定財産承継遺言」とは何か、その特徴や活用方法、そして「特定遺贈」との違いを明確にした上で、遺言書を作成する際の注意点を詳しく解説していきます。相続トラブルを未然に防ぐためにも、これらの制度を正しく理解し、法的に有効な遺言を残すための参考にしてください。
特定財産承継遺言とは
民法上の遺言形式の一種で、遺言者が自身の財産の中から特定の財産を指定し、それを特定の相続人に承継させることを明確に記した遺言です。ここでいう「承継させる」という表現には、法的に特別な意味があります。
この遺言では、法定相続人の中から受け取る人を指定し、その人に具体的な財産を「相続させる」と明記する必要があります。たとえば以下のような記述です。
- 「長男○○には、自宅(東京都○○区○丁目○番地の土地及び建物)を相続させる」
- 「次男○○には、○○銀行○○支店の普通預金(口座番号:12345678)の全額を相続させる」
- 「長女○○には、私が所有する○○株式会社の株式500株を相続させる」
財産の種類と範囲、相続人の氏名などを具体的に記載し、「相続させる」と明記することで、特定財産承継遺言としての効力が発生します。
特定財産承継遺言の最大の特徴は、その法的効力です。遺言が有効である限り、指定された相続人は、相続開始(遺言者の死亡)と同時に、対象財産の所有権を自動的に取得します。このため、不動産登記の際にも他の相続人の同意や遺産分割協議書は不要となり、単独での手続きが可能になります。
また、特定財産承継遺言の背景には、被相続人の意志を正確に反映するという強い目的があります。たとえば「家業を継ぐ長男に事業用不動産を継がせたい」「特定の子には経済的に配慮したい」といった具体的な希望を、法的に確実に実現させるための手段として活用されます。
一方で、この遺言方式にはいくつかの注意点もあります。文言の誤りや財産の記載ミス、遺留分とのバランスを欠いた指定などがあると、トラブルや無効のリスクが生じます。
特定財産承継遺言は、遺産分割協議を回避したい、または明確に財産の承継先を定めておきたいというケースにおいて、非常に有効な制度です。しかし、その効果を正しく発揮するためには、法的に正確で、内容の明確な遺言書を作成することが求められます。
一般的な相続の流れと比較
特定財産承継遺言の効力やメリットを理解するには、まず一般的な相続の手続きとの違いを明確にする必要があります。以下に、遺言がない場合と、特定財産承継遺言がある場合の相続の流れを比較します。
比較項目 | 遺言なし(法定相続) | 特定財産承継遺言あり |
財産の承継方法 | 相続人全員による遺産分割協議が必要 | 遺言の内容に従い、対象相続人が自動的に取得 |
手続きの煩雑さ | 協議書の作成、全員の署名・押印が必要 | 対象相続人が単独で登記・名義変更可能 |
所有権の移転時期 | 遺産分割協議成立時点 | 相続開始時(遺言者の死亡時)に自動的に発生 |
トラブルの可能性 | 高い(意見の対立、感情的な衝突など) | 低い(承継内容が明示されているため) |
遺言が存在しない場合、たとえ相続人同士が良好な関係であっても、遺産分割協議の過程で対立が生じることは珍しくありません。たとえば、実家の不動産を誰が相続するか、預金をどのように分けるかなどの点で争いになりやすく、最終的に家庭裁判所での調停に発展するケースもあります。
一方、特定財産承継遺言がある場合、遺産の一部についてはその遺言の指示通りに自動的に相続が行われるため、協議自体が不要となります。とくに不動産や有価証券など、所有権の移転手続きにおいて法的根拠が必要な資産においては、遺言があることで相続手続きが非常にスムーズになります。
また、銀行口座の解約や名義変更においても、遺言執行者を指名しておけば、煩雑な同意書の取り付けや家族間の連絡調整を最小限に抑えることができます。これにより、相続人の精神的・時間的負担を大幅に軽減できるのが、特定財産承継遺言の大きな利点です。
つまり、相続の「見える化」を事前に図ることで、相続手続きそのものの透明性と効率性を高めることができるのです。この点が、法定相続との大きな違いと言えるでしょう。
特定財産承継遺言のメリット
特定財産承継遺言は、被相続人と相続人の双方にとって多くのメリットをもたらします。特に、遺言者の意思を法的に確実に実現できる点や、相続人間のトラブルを防ぎやすい点は見逃せません。以下に、被相続人と相続人それぞれの立場から、その利点を詳しく見ていきましょう。
被相続人にとってのメリット
意思を明確に反映できる
特定財産承継遺言は、単なる「財産を渡す」という意思表示にとどまらず、具体的に「何を誰に渡すか」を明記することで、被相続人の意思をより正確に形にすることができます。たとえば、「長男には家業を継がせたいから店舗を」「長女には老後の世話をしてくれた感謝として預金を」といった細やかな配慮を遺言に反映できます。
承継先の希望が明確に実現する
単に「全財産を分ける」のではなく、「特定の財産を特定の人に」とすることで、自身の価値観や家族の事情に即した相続設計が可能になります。たとえば、居住用不動産はそこに住み続ける子に残し、経済的支援が必要な子には流動性の高い金融資産を分けるなど、合理的かつ公平感のある相続配分が実現します。
遺産分割協議によるトラブルの回避
明確な意思表示があることで、遺産分割協議を巡る感情的な対立を未然に防ぐことができます。親の意思に反するような相続分配が行われることもなく、相続人が主観的な解釈に基づいて主張し合うリスクも低減します。結果として、遺言者の死後に家族間の関係が悪化するのを防ぐ効果もあります。
相続人にとってのメリット
スムーズな財産取得が可能
遺産分割協議を経ることなく、遺言の内容に基づいてすぐに相続手続きを進めることができます。たとえば、特定の不動産を相続した相続人は、単独での登記申請が可能になり、名義変更の手続きも迅速に行えます。
手続きの簡略化と費用の抑制
通常、遺産分割協議書の作成や司法書士による相続登記などには時間も費用もかかります。特定財産承継遺言があれば、登記の際に他の相続人の同意書を集める必要がなくなり、弁護士費用や調停費用など、将来的な法的トラブルにかかるコストも抑えられます。
心理的な安心感
「自分にはこれが相続される」と明確に書かれていることで、他の相続人との関係においても精神的な安定が得られます。とくに不動産のような分割が困難な資産では、誰が取得するかが曖昧なままでは争いの種となりますが、特定財産承継遺言によりその不安は解消されます。
以上のように、特定財産承継遺言は、相続人の数が多い場合や、財産の種類が多様な場合において、その効果を最大限に発揮します。被相続人の意思と、相続人の利益が両立する、きわめて実用性の高い相続手段であると言えるでしょう。
特定財産承継遺言と特定遺贈の違い
特定財産承継遺言と非常に似た概念に「特定遺贈」があります。いずれも、遺言によって特定の財産を特定の人物に与えるという点では共通していますが、法的性質や相続手続き上の取り扱いには大きな違いがあります。特定財産承継遺言が相続人に対して用いられるものであるのに対し、特定遺贈は相続人以外の第三者にも適用されるという点も重要です。
以下の比較表で、両者の主な相違点を整理します。
項目 | 特定財産承継遺言 | 特定遺贈 |
財産の受取人 | 相続人(子、配偶者など) | 相続人・第三者(友人、内縁の配偶者、法人など) |
使用する文言 | 「相続させる」 | 「与える」「贈与する」「譲る」など |
所有権の移転時期 | 相続開始と同時に自動的に移転 | 相続人の受け入れにより成立(登記等に他の相続人の協力が必要な場合あり) |
相続手続きの必要性 | 単独で登記や名義変更が可能 | 相続人全員の同意・手続きが必要なケースがある |
相続税の課税対象 | 相続財産として課税される | 遺贈財産として課税される(課税額に差異あり) |
遺留分との関係 | 遺留分を侵害すると請求対象になる | 同様に、遺留分侵害があれば請求対象となる |
このように、両者は似て非なるものであり、何よりも重要なのは「遺言書に使われる文言の違い」です。たとえば、遺言書に「長男に自宅を与える」と書いてしまった場合、民法上は「遺贈」とみなされる可能性が高くなります。すると、相続人全員の合意がなければ不動産の登記ができないといった事態が生じ、被相続人の意思が十分に実現されない可能性もあります。
一方、特定財産承継遺言として「相続させる」と明記されていれば、その相続人は単独で所有権を取得し、登記の手続きも一人で進めることができます。この違いは、実際の相続実務において大きな影響を与えるため、遺言書を作成する際には法的表現の使い分けが極めて重要になります。
また、特定遺贈は、例えば内縁の配偶者や長年支えてくれた友人など、法定相続人ではない人物に財産を残したい場合に有効な手段ですが、登記や名義変更においては、相続人の協力が必要となることがあるため、その実現性には注意が必要です。
さらに、税務上の扱いについても、相続人が取得する場合と、第三者が遺贈を受ける場合とでは、相続税の課税対象や控除の範囲が異なるため、税理士と相談しながら設計することが望ましいです。
このように、特定財産承継遺言と特定遺贈は、表面的には似ていても、内容・効果・手続きのすべてにおいて異なる法的構造を持っています。したがって、遺言者の意思を正確に実現するためには、単語一つひとつにも配慮した慎重な遺言書作成が求められます。
作成時の注意点
特定財産承継遺言を作成する際には、法的効力を確保し、後のトラブルを回避するために数多くの点に注意を払う必要があります。単に「遺言書を残せば良い」というわけではなく、その内容が法律に即しており、かつ実務上も確実に機能するものでなければ、遺言者の意図が適切に実現されない可能性が高まります。ここでは、遺言書作成における具体的な注意点について解説します。
文言は「相続させる」と明確に書く必要がある
前述の通り、特定財産承継遺言としての法的効力を発生させるには、「相続させる」という明確な表現を用いることが不可欠です。たとえば、「長男に自宅を譲る」や「次男に預金を与える」などと記載した場合、それが遺贈と判断され、特定財産承継遺言としての効力を失う可能性があります。このような表現の揺れは、相続人間の解釈の違いを生み、結果として相続争いの原因になります。
特に、相続人に特定の財産を承継させる意図がある場合には、「相続させる」という法律用語を正確に使用することが必要です。言い回しひとつで手続きの難易度が大きく変わるため、慎重な文言選定が求められます。
遺言の解釈を巡り争いが起こる可能性があるため、具体的に記載することが重要
遺言は、相続人に対して強い法的拘束力を持ちますが、その一方で、曖昧な表現が含まれている場合、相続人間でその意味を巡って争いが発生することがあります。
たとえば、「預金を相続させる」と書かれていた場合、どの銀行のどの口座を指しているのかが不明確であると、相続人が複数の口座を巡って解釈を争うことになりかねません。したがって、「○○銀行○○支店 普通預金口座番号1234567に係る預金の全額を相続させる」といった具合に、財産の内容を特定しやすい形で記述することが重要です。
遺留分を侵害すると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがある
法定相続人には、最低限の相続分である「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。たとえば、配偶者や子どもがいる場合、各人の遺留分を超えて他の相続人に偏った相続をさせた場合には、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。
たとえ特定財産承継遺言が法的に有効であっても、遺留分を大きく超える内容であった場合、法的紛争の火種となることがあります。このリスクを軽減するためには、各相続人の遺留分を事前に計算し、それを侵害しない範囲で遺言内容を構成することが理想的です。
また、もし遺留分を侵害する内容にならざるを得ない事情がある場合(たとえば事業継承のための資産集中など)は、遺留分のある相続人との生前の合意や調整を行っておくことが重要です。
不動産や金融資産の特定は正確に
不動産や預貯金、有価証券などの財産を承継させる場合には、対象となる財産を明確かつ正確に記載する必要があります。たとえば不動産については、所在地だけでなく、登記簿に記載されている地番や建物の構造、面積なども記載しておくと良いでしょう。
具体例:
「東京都新宿区○○1丁目1番1 土地 地目:宅地 地積:150.00㎡」
「同所所在の建物 木造2階建 延床面積120.00㎡」
預貯金の場合は、金融機関名、支店名、口座の種別(普通・定期など)、口座番号まで記載することが望ましいです。このようにすることで、遺言の実行段階において解釈の余地がなくなり、スムーズな手続きが可能になります。
必ず有効な遺言形式を選び、専門家のチェックを受けるのが安心
遺言には複数の形式があり、一般的には以下の3種類が用いられます。
- 自筆証書遺言(遺言者が全文、日付、署名を自筆で記載)
- 公正証書遺言(公証人が作成、証人2人の立ち会いが必要)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にしながらも公証役場で保管可能)
とくに、自筆証書遺言は形式不備によって無効とされるリスクが高いため、2020年から開始された「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用するのが望ましいです。より確実性を求めるのであれば、公証人の関与により作成される公正証書遺言が最も信頼性の高い形式といえます。
また、どの形式を選ぶ場合でも、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)による内容のチェックを受けることで、誤解を招かない表現や、法的に矛盾のない遺言書とすることができます。
これらの注意点をすべて押さえることで、特定財産承継遺言の法的効果を最大限に発揮し、遺言者の意志が確実に反映される遺言書が完成します。安易に自己判断で作成するのではなく、可能な限り専門的な知識を活用する姿勢が、最も堅実な相続対策につながるのです。
まとめ
特定財産承継遺言は、自身の財産を誰にどのように承継させたいのか、その意思を明確に形にできる法的手段の一つです。とくに、不動産や預貯金、有価証券などの個別の資産を、特定の相続人にスムーズに引き継がせたいという意図を持つ場合に非常に効果的です。
一般的な相続手続きでは、すべての相続人が協議して遺産を分割する必要があり、時に感情的な対立や法的な争いに発展することもあります。しかし、特定財産承継遺言を適切に活用すれば、そのような協議を一部または全面的に回避することが可能になります。遺言の効力が発生した時点で、指定された相続人にその財産の所有権が自動的に移転するため、相続手続きが格段に簡潔になり、相続人にとっても精神的・時間的な負担を大幅に軽減することができます。
ただし、この遺言形式を正しく機能させるためには、いくつかの重要な条件があります。「相続させる」という正確な文言の使用、財産の明確な特定、そして遺留分の考慮です。これらを怠ると、意図した通りに相続が行われず、かえって相続人同士の対立を招く原因にもなり得ます。また、遺言書の形式や保管方法によっては、遺言そのものが無効と判断されるリスクもあるため、形式的要件の確認も不可欠です。
さらに、特定財産承継遺言と似た概念である特定遺贈との違いについても十分に理解しておく必要があります。文言や受取人の違いによって手続きの流れが大きく異なるため、誤った記述を避けるためにも専門家による確認が望まれます。
最終的には、信頼できる専門家――弁護士や司法書士、税理士など――のサポートを受けながら、法的に問題のない遺言書を作成することが、円満な相続と家族の将来を守る最善の方法となるでしょう。特定財産承継遺言は、相続におけるトラブルを未然に防ぎ、相続人それぞれの立場や役割を尊重しながら、公平かつ円滑な承継を実現するための、極めて有効な選択肢の一つなのです。
関連記事
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

iPhoneの「故人アカウント管理連絡先」は使える? 万が一に備えた対応

遺骨ダイヤモンドとは?アルゴダンザ・ジャパン社へ伺いました

国際結婚したカップルは同じお墓に入れるの?最近の傾向をふまえて解説

終活サポート ワンモア今井代表に聞いた|終活の意識変化と今後。一歩を踏み出すためのアドバイス

20代以上の男女300人に聞いた「終活の意識調査」

年末調整では医療費控除できない?確定申告との違いと正しい申請方法をわかりやすく解説

故人のPayPayやSuicaなど電子マネーは相続できる?残高確認と手続きの流れを徹底解説

家系図作成はプロに任せて安心!調査の正確性・対応範囲・料金・納品形式で徹底比較|信頼できる主要5業者を詳しく紹介