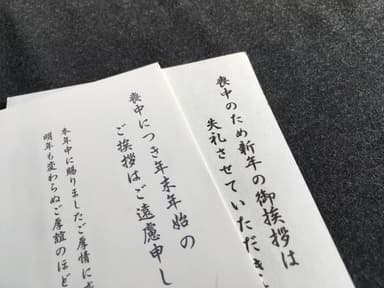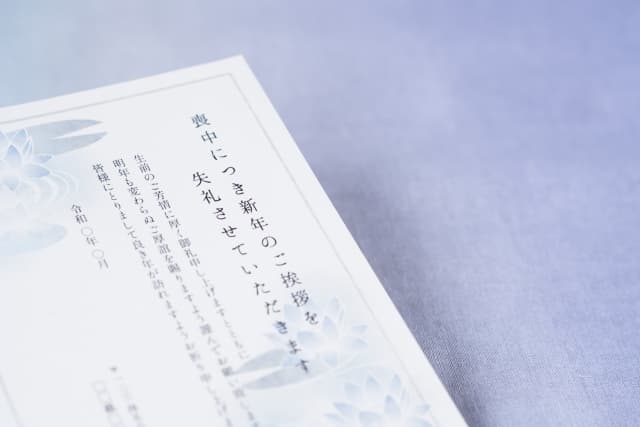
喪中のときの年賀状対応はどうする?迷わないためのマナーと対応例を解説
公開日: 更新日:
年末年始といえば、日本では年賀状のやりとりが恒例行事となっています。新しい年の始まりを祝福し、日頃の感謝や今後のご縁をつなぐ手段として、年賀状は古くから大切にされてきました。しかし、身内に不幸があった場合、年賀状を控えるという“喪中”の習慣があります。とはいえ、「喪中の範囲ってどこまで?」「喪中はがきは誰に送ればいいの?」「喪中なのに年賀状が届いたらどうすれば?」など、実際にはわからないことが多いのも事実です。
特に最近では、家族のかたちが多様化しており、喪中に該当する範囲や対応の仕方も一律ではありません。また、年賀状を出す文化自体が縮小傾向にある今、改めて喪中時の年賀状マナーを見直すことには大きな意味があります。
喪中は、ただ形式的に年賀状を控えるだけではなく、「哀しみを共にする」あるいは「相手への心遣いを形にする」という、思いやりの文化でもあります。だからこそ、曖昧なまま対応してしまうと、かえって相手に不快な思いをさせてしまう可能性もあるのです。
喪中というデリケートな時期だからこそ、形式にとらわれすぎず、相手への敬意と配慮を忘れずに対応することが大切です。このコラムを通して、あなた自身や大切な人たちが心穏やかに新年を迎えるための一助となれば幸いです。
喪中の定義と範囲
「喪中」とは、一般的に身内に不幸があった際に喪に服する期間を指します。これは、故人を悼み、心静かに過ごすための時間であり、日本文化における弔いの慣習の一部として根付いています。この喪中期間中は、祝い事や華やかな行事を控えるのが礼儀とされており、年賀状のやりとりもその一つです。
では、どの範囲の親族が亡くなった場合に「喪中」とするべきなのでしょうか?
一般的な喪中の対象範囲
喪中の対象となる範囲に明確な法律上の決まりはありませんが、伝統的には二親等以内の親族が対象とされています。以下が代表的な喪中対象者です。
続柄 | 親等 | 喪中対象の一般性 |
配偶者 | 0 | ○ 必ず喪中にする |
父母 | 1 | ○ 一般的に喪中 |
子ども | 1 | ○ 一般的に喪中 |
兄弟姉妹 | 2 | ○ 多くは喪中 |
祖父母 | 2 | ○ 多くは喪中 |
孫 | 2 | △ 個人判断 |
叔父・叔母 | 3 | △ 関係による |
いとこ | 4 | × 原則喪中外 |
※「親等」は民法上の血縁関係の近さを表すもので、0等が配偶者、1等が直系の親子関係、2等が兄弟姉妹や祖父母などに当たります。
喪中の判断は“気持ち”が優先されることも
形式上は二親等以内が目安とされていますが、実際のところは故人との関係性や想いの深さによって喪中とするかどうかを判断する人も少なくありません。
たとえば、長年同居していた叔母が亡くなった場合、三親等であっても喪中と考え喪中はがきを出す方もいます。逆に、疎遠だった祖父母の死去に際して喪中としないこともあります。
喪中期間はいつまで?
日本では一般的に喪中の期間は故人が亡くなってから1年間とされています。ただし、これは厳密なルールではなく、「翌年の正月を迎えるまで」を喪中とするケースもあります。
仏教では「四十九日」、神道では「五十日祭」などを節目に忌明け(きあけ)とすることがありますが、それを過ぎても年賀状だけは喪中を理由に差し控えるのが一般的なマナーです。
仕事上の付き合いや友人関係では?
仕事上の取引先や、年賀状だけのやりとりをしている相手に対しても、自分が喪中であることを伝えるかどうかは迷うところです。しかし、基本的には「前年に年賀状をいただいた相手」には喪中はがきを出すのが丁寧とされています。喪中の範囲に入る親族が亡くなった場合は、ビジネスシーンでも失礼のないよう早めに対応しましょう。
喪中の定義と範囲が理解できていれば、次に考えるべきは「誰にどのように喪中を伝えるか」というマナーです。
喪中はがきを出すときのマナー
ここでは、誰に・いつ・どのように喪中はがきを出すべきかについて詳しく見ていきましょう。
誰に出すべきか?送付先の選び方
喪中はがきは、以下のような相手に送るのが一般的です。
- 前年に年賀状をやりとりした相手
最も基本的な対象です。喪中はがきは「今年は年賀状を控えます」という意思表示であり、やりとりのある相手に送るのが自然です。 - 近年、年賀状を出していないが交流のある相手
冠婚葬祭で交流があった、今後の付き合いを大切にしたい相手にも送ると良いでしょう。 - 仕事関係者や上司・恩師など礼儀を重視したい相手
形式的なやりとりであっても、マナーとして知らせることが望ましいとされています。 - 相手から年賀状が届く可能性が高い場合
喪中を知らずに年賀状を送ってしまうと、相手に気まずい思いをさせることがあります。そういった配慮から送付対象を広げる人も少なくありません。
送る時期とタイミング
喪中はがきは11月中旬から12月初旬までに先方に届くよう送るのが理想です。
これは、一般的に年賀状の準備を12月中旬から始める人が多いため、それまでに知らせることで相手が年賀状を控えることができるからです。
送付時期の目安 | 内容 |
10月末〜11月上旬 | 故人が早い時期に亡くなった場合、早めに通知するのが適切です |
11月中旬〜下旬 | 最も一般的な送付タイミング |
12月上旬 | ギリギリではありますが、まだ間に合います |
12月中旬以降 | なるべく避けたいが、訃報が遅れた場合はやむを得ない |
喪中はがきの形式と印刷方法
喪中はがきには、次の2つの方法があります。
- 自作(手書き・PC作成):文章に個人の気持ちを込めたい方におすすめ。
- 印刷業者への依頼:短期間で多数のはがきを準備したい場合に便利。
多くの印刷業者では、文例のテンプレートが用意されており、氏名・故人との続柄・差出人情報を入力するだけで簡単に注文できます。
喪中でも年賀状を出したい相手がいる場合は?
基本的に喪中の間は年賀状を控えるべきですが、どうしても感謝の気持ちを伝えたい相手がいる場合には、年が明けてから寒中見舞いとして送ることができます。これについては後ほど詳しく紹介します。
喪中はがきの書き方
喪中はがきは、「新年のご挨拶を控える旨を丁寧に伝える」ためのものです。過度に感情的にならず、しかし形式的すぎず、故人を悼む気持ちと相手への配慮を両立させた文章を心がけることが大切です。
この章では、喪中はがきにふさわしい文面の基本構成や書き方のマナー、具体的な文例をわかりやすく紹介します。
喪中はがきの基本構成
喪中はがきの文章は、以下のような4つの要素で構成されるのが一般的です
- 時候の挨拶(省略されることもある)
季節に応じた挨拶文ですが、喪中はがきでは省略しても問題ありません。 - 訃報の内容
誰がいつ亡くなったのかを簡潔に伝えます。故人の氏名ではなく、「父」「祖母」などの続柄を記載するのが一般的です。 - 年賀欠礼の旨と感謝の気持ち
年賀状を控えることを伝えるとともに、生前のお付き合いに対する感謝の言葉を述べます。 - 今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉
これからも良い関係を築いていきたいという気持ちを添えると、より丁寧な印象になります。
喪中はがきの基本文例
喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます
本年○月に母 ○○が永眠いたしました
ここに本年中に賜りましたご厚情を深謝いたしますとともに
明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます
このように、簡潔かつ丁寧な表現が理想的です。喪中はがきは哀悼の意を伝えるものですが、感情表現を控えめにすることで、受け取る側に負担をかけない文面になります。
表現上のマナーと注意点
喪中はがきには、独特のマナーがあります。以下のポイントを押さえて、失礼のない文章を心がけましょう。
- 句読点は使用しない
お祝いごとや弔事の文面では、句読点は「区切り」や「終わり」を連想させるため、使わないのが慣例です。 - 故人の氏名は書かない
喪中はがきでは故人の名前は記さず、「母」「祖父」などの続柄のみを使用します。 - 忌み言葉を避ける
「死」「苦」「終わる」「消える」など、不吉とされる言葉は避け、「永眠する」「逝去」など柔らかい表現を使いましょう。 - 過度な感情表現は控える
あくまで年賀欠礼の通知であり、個人的な悲しみや詳細な経緯を綴る手紙ではないため、感情的な表現は避けましょう。
差出人情報の記載方法
文面の最後には、差出人の名前と住所を忘れずに記載します。家族全員で出す場合は「○○家」と記載しても構いませんし、個人で出す場合はフルネームを明記します。
差出人欄は、文面の下部中央に住所→氏名の順で配置されることが多いです。
喪中はがきの注意点
1. 喪中に該当しない場合でも出してしまうケース
喪中はがきは、原則として二親等以内の親族が亡くなった際に送るものですが、親しい親戚や家族同然の関係にあった人物の死去に際して、形式を超えて喪中の意を示すことがあります。
しかし、明確に喪中に該当しない続柄で出す場合は、相手に「どうして?」と思わせないよう、配慮した文面やタイミングを心がける必要があります。
例えば、いとこや親しい友人など、三親等以降の人物の訃報に際して喪中はがきを送る場合は、「長年同居していた○○が逝去したため、本年は年始のご挨拶を控えさせていただきます」のように、背景を簡潔に添えると誤解を防ぐことができます。
2. 訃報が年末近くになった場合の対応
12月中旬以降に身内の不幸があった場合、相手がすでに年賀状を投函していることも考えられます。この場合、喪中はがきを慌てて出すのではなく、年が明けてから寒中見舞いとして事情を伝えるのが一般的です。
喪中はがきは「事前に知らせる」ことが目的のため、すでに相手が年賀状を用意している時期では意味をなさないこともあります。そうしたときは、「昨年末、○○が永眠いたしました。ご挨拶が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」といった一文を添えた寒中見舞いで対応すると、丁寧な印象を与えられます。
3. 喪中はがきを送る人数が多い場合のミス
数十枚〜百枚単位で喪中はがきを出す場合、以下のようなミスが起こりやすくなります
- 差出人の名前や住所の記載ミス
- 同じ相手に複数送ってしまう
- 年賀状と混同して誤って送る
これを防ぐためには、事前に送付リストを整備し、チェックリスト形式で管理することが大切です。印刷業者に依頼する場合でも、差出人情報はしっかり確認しましょう。
4. 近況報告や個人的な話題は控える
喪中はがきは、あくまで「年賀欠礼のご挨拶」です。年賀状とは異なり、家族の近況報告や写真、趣味の話題などを含めるのは適切ではありません。
たとえば、
- 「娘が高校に合格しました」
- 「家族で海外旅行に行きました」
- 「新しい趣味を始めました」
といった話題は、喪中という弔意を示す場面にはふさわしくないため、避けるようにしましょう。
相手にとっては年賀状感覚で読まれることもありますが、受け取った側が違和感を覚える恐れがあるため、喪中はがきでは個人的な情報は最小限に抑えるのがマナーです。
喪中で年賀状を受け取った場合
年末年始の挨拶が習慣となっている日本では、喪中であることを知らなかった相手から年賀状が届くことがあります。
こうしたとき、どう対応するべきか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、喪中に年賀状を受け取った際の対応について、実用的な視点から解説します。
1. 喪中でも年賀状は受け取れる?
結論から言えば、喪中であっても年賀状を受け取ること自体に問題はありません。
喪中とは、あくまで自分が新年の挨拶を控える期間であり、相手に対して挨拶を禁じるものではないためです。
たとえば、相手が自分の喪中を知らずに年賀状を送ってきた場合、それを咎めたり不快に感じたりする必要はありません。
むしろ、「喪中であることを事前にお知らせしなかったこと」や、「相手が気を遣わずに済んだこと」に対して、感謝の気持ちで受け取るのが大人の対応といえます。
2. 喪中はがきを受け取った場合にはどうするか?
年末に喪中はがきを受け取った場合、多くの方が「この人には年賀状を送ってよいのだろうか」と戸惑います。
結論から言えば、喪中はがきを受け取った相手には年賀状を控えるのが礼儀です。喪中とは、祝い事を控える期間であり、年始の挨拶も遠慮したいという相手の意思を尊重する必要があります。
年賀状の代わりに「寒中見舞い」で心遣いを伝える
年賀状を控えた後、代わりに送るのが寒中見舞いです。
寒中見舞いは季節の挨拶状であると同時に、喪中の方への配慮を伝える手段でもあります。形式的な挨拶になりすぎず、やさしい気持ちを伝えることができます。
寒中見舞いの基本ルール
- 送る時期:1月7日〜2月初旬(立春)まで
- 目的:新年の挨拶を遠慮したことへのお詫びと、相手の健康を気遣うメッセージ
- 文面の内容:哀悼の意を示す必要はありませんが、相手の心情に寄り添う表現を心がけましょう
文例紹介
寒中お見舞い申し上げます。
ご服喪中と伺い、新年のご挨拶を控えさせていただきました。
寒さ厳しき折、どうぞご自愛のほどお祈り申し上げます。
あるいは、より個人的なメッセージを添えたい場合は
このたびはご不幸のこと、心よりお悔やみ申し上げます。
寒さも厳しくなってまいりましたが、どうかお身体にお気をつけてお過ごしください。
まとめ
喪中とは、故人を偲びつつ、祝い事を控える日本の大切な慣習です。形式的に年賀状を出さないというだけでなく、故人への哀悼と相手への配慮を伝える機会でもあります。そのため、喪中の範囲や対応は、単なるマナーではなく、人間関係を大切にするための心遣いが求められます。
喪中はがきを出すのは、主に年賀状のやりとりがある相手に対してで、11月中旬から12月上旬に届くよう送るのが望ましいとされています。文面は簡潔に、感情的な表現や忌み言葉を避け、相手に負担をかけないよう配慮します。
また、喪中に年賀状を受け取った場合、それを問題視する必要はなく、寒中見舞いで感謝の気持ちを伝えるのが丁寧な対応です。一方で、喪中はがきを受け取った場合には、その相手には年賀状を控え、寒中見舞いでご挨拶するのが礼儀とされています。
喪中のマナーは、決まりごとに見えて、実は「思いやりの心」が最も大切です。形式にとらわれすぎず、相手の立場に寄り添う姿勢を忘れずに対応したいものです。
関連記事
この記事を共有