
供花の意味と重要性:供花と献花の違いも含めて解説
公開日: 更新日:
葬儀や追悼の場で耳にする「供花(くげ・きょうか)」と「献花(けんか)」。いずれも花を用いて故人を偲ぶ行為として重要ですが、その意味や使用される場面、作法には明確な違いがあります。知らずに使い分けを間違えると、遺族や参列者に失礼となる場合もあります。
本記事では、供花と献花の基本的な意味や違い、それぞれの手配方法や適切なマナーについて詳しく解説します。葬儀や追悼の場で適切に振る舞うための知識をしっかりと身につけましょう。
供花とは?基本の意味と贈る際のマナー
供花とは、葬儀や法事の際に故人の霊前や祭壇に供える花のことを指します。
供花の目的
1.故人への哀悼の意を示す
供花は「安らかにお眠りください」「あなたを忘れません」といった敬意や祈りを込めて供えるものです。
2.遺族への慰め
供花を贈る行為は、遺族に対して「悲しみを共有しています」という連帯感や励ましのメッセージを伝える意味もあります。
3.葬儀場の装飾
白や淡い色の花で構成された供花は、葬儀の空間を厳粛で清らかな雰囲気に整える役割を果たします。
供花に使用される花の種類
供花に使われる花は、宗教や形式によって異なりますが、白を基調とした落ち着いた色合いが一般的です。
仏式・神式の葬儀
・白菊や輪菊:仏教では不変や高潔の象徴とされ、定番の花です。
・百合(カサブランカなど):清楚で気品があり、仏式・神式どちらでもよく用いられます。
・紫や青、淡いピンクの差し色:白を基調としつつ、落ち着いた色を少し加えることで、花全体に彩りを添えます。
・故人の好きな花:故人が好んでいた花を取り入れることもあります。
また、生花の代わりに造花やプリザーブドフラワーが使用されることもあり、これらは管理がしやすく、長期間飾れるため便利です。
キリスト教の葬儀
・白やピンクの百合:キリスト教では純潔や復活の象徴とされる百合が定番です。
・カーネーション:やさしい印象の白やピンクのカーネーションが選ばれることが多いです。
・小菊やスプレー菊:仏式で用いる大ぶりの菊ではなく、小ぶりのものが適しています。
ただし、キリスト教の葬儀では造花は使用できない点に注意が必要です。生花のみが使用されるのが一般的です。
供花の形式
供花にはいくつかの形式があります。それぞれ特徴が異なるため、状況に応じた選び方が重要です。
・スタンド花
高さのあるスタンド型で、豪華さや荘厳さを演出します。特に大規模な葬儀や団体から贈られる場合に適しており、祭壇を取り囲むように設置されることが多いです。
・アレンジメントフラワー
低めの器に花をまとめた形式で、スペースを取らず、設置しやすいのが特徴です。個人や小規模なグループから贈られることが多く、控えめで落ち着いた印象を与えます。
献花とは?
献花(けんか)とは、故人への追悼や祈りを込めて花を捧げる行為そのものを指します。葬儀や追悼式などで行われるこの儀式は、宗教や文化を問わず広く用いられ、故人への敬意や感謝、祈りを表現する重要な意味を持っています。
献花の目的
献花には次のような目的があります。
1.故人への敬意と感謝を表す
献花を通じて、故人に対する祈りや敬意、感謝の気持ちを伝えます。キリスト教式の葬儀では、献花が重要な儀式の一部として行われ、純潔や復活の象徴とされる花を捧げることで、故人の魂の平安を願います。
2.祈りや平和の象徴
献花は個人の追悼に留まらず、平和や祈りの象徴として広く行われます。戦没者や事故の犠牲者を追悼する場で、参列者が献花を通じて気持ちを共有することは、儀式全体を厳粛なものにする役割を果たします。
献花に使用される花の種類
献花で用いられる花には特徴があります。白を基調としたシンプルな生花が一般的であり、造花は避けられるのが基本です。捧げる際に両手で花を持つため、扱いやすい形状や特性を持つ花が選ばれます。
よく使用される花
・白い百合
清らかで純粋な印象を与え、キリスト教式の献花でも定番です。香りが強すぎない種類が好まれます。
・白いカーネーション
やさしい印象を持ち、葬儀や追悼式で広く用いられる花です。
避けるべき花
・棘のある花
バラのように棘がある花は、両手で扱う際に不便であるため避けるのが一般的です。
・茎がない花や短い花
献花台に捧げる際に茎が短いと扱いにくいため、長い茎のある花が適しています。
・しおれやすい花
長期間飾られることを想定し、しおれにくい花を選ぶことが推奨されます。
供花と献花の違い
供花と献花は、どちらも花を通じて故人への追悼を表すものですが、明確な違いがあります。ここでは「手配方法」「花の種類」「金額」「葬儀形式」の4つの観点から違いを詳しく解説します。
手配方法の違い
供花
供花は事前に花屋や葬儀場を通じて手配します。通夜や葬儀の開始前までに会場へ届けるのが基本です。贈り主の名前や団体名が記載された札を添えるのが一般的で、インターネットでの注文も広く利用されています。
・手配先:花屋、葬儀場、オンラインサービス
・タイミング:葬儀や通夜開始前に手配し、会場に届ける
献花
献花は通常、葬儀や追悼式の場で参列者に配布される一輪の花を使用します。個人で持参する場合も、一輪の花を準備するだけで済みます。会場で事前に用意されることが多いため、個別の手配は必要ありません。
・手配先:会場で配布、または一輪の花を用意
・タイミング:当日会場で配布されることが一般的
花の種類の違い
供花
供花には、仏式や神式の葬儀では白を基調とした花(菊や百合など)が一般的に使われます。故人の好きな花を取り入れることもありますが、全体的に落ち着いた色合いが好まれます。生花のほか、造花やプリザーブドフラワーが用いられる場合もあります。
・仏式・神式:白菊、百合、トルコキキョウなどの白や淡い色の花が中心
・キリスト教式:白やピンクの洋花(百合、カーネーション)が主流
献花
献花では、扱いやすく持ちやすい一輪の花が選ばれます。棘のある花(例:バラ)や茎の短い花は避けられ、茎が長くしおれにくい白い百合やカーネーションがよく用いられます。必ず生花を使用し、造花は不適切とされます。
・主な花の種類:白い百合、カーネーション、棘のないバラなど
・注意点:茎が長く、しおれにくい花を選ぶ
金額の違い
供花の費用
供花は、花の種類やアレンジの規模によって金額が異なります。個人で贈るアレンジメントフラワーは5,000円~1万円程度、大規模な葬儀で使用されるスタンド花は1基あたり1万5,000円~3万円程度が目安です。スタンド花は通常一対(二基)で贈られるため、その場合の費用は3万円~6万円となります。
・アレンジメントフラワー:5,000円~1万円程度
・スタンド花:1万5,000円~3万円(一基)
献花の費用
献花の花自体は1本あたり300円~500円程度と非常に安価です。通常、献花の花は会場が用意し、葬儀プランの一部に含まれているため、参列者が負担することはほとんどありません。ただし、キリスト教式の葬儀では香典の代わりに「御花料」をご遺族に渡す習慣があります。
・御花料の相場
両親・義両親:5万円~10万円
兄弟姉妹:3万円~5万円
祖父母:1万円~3万円
友人・知人:3,000円~1万円
勤務先の上司・同僚:3,000円~1万円
葬儀形式の違い
供花
供花は仏式や神式の葬儀で中心的に用いられる花です。会場の装飾として祭壇や遺影の周囲に飾られ、故人への哀悼の意を表すとともに、会場全体を荘厳な雰囲気に整えます。キリスト教式の葬儀では供花が使用されることもありますが、主に補助的な役割を果たします。
・仏式・神式:供花が中心
・キリスト教式:使用される場合もあるが補助的な役割
献花
献花はキリスト教式の葬儀や無宗教の追悼式で重要な儀式の一部として行われます。全参列者が一輪の花を捧げることで、故人への祈りや追悼の意を表します。また、戦没者や事故犠牲者を追悼する公共の場でも行われることが多く、平和や祈りを象徴する行為とされています。
・キリスト教式:儀式の重要な部分として行われる
・無宗教式・追悼式:宗教を問わず広く受け入れられる
供花と献花の比較表
項目 | 供花 | 献花 |
|---|---|---|
手配方法 | 花屋や葬儀場で事前に手配し、会場に届ける | 会場で配布される花を使用、または一輪を用意 |
花の種類 | 白菊、百合、トルコキキョウ、洋花など | 白い百合、カーネーション、棘のないバラなど |
金額 | アレンジメント:5,000円~1万円、スタンド花:1万5,000円~3万円 | 献花の花:300円~500円、御花料:3,000円~10万円 |
葬儀形式 | 仏式・神式で中心的な役割を果たす | キリスト教式や無宗教式で重要な儀式として行われる |
供花の手配方法や送る際の注意点
供花は、葬儀や法事の場において故人への哀悼の意を表す大切な贈り物です。しかし、適切な手配やマナーを守らないと遺族に迷惑をかけたり、失礼にあたったりする可能性があります。ここでは、供花の手配方法や注意点について詳しく解説します。
供花の手配方法
供花を手配する方法は主に以下の3つです。
1.葬儀社に依頼する
葬儀を担当する葬儀社に供花の手配を依頼するのが、最も一般的かつ簡単な方法です。葬儀の形式や会場のスペースを熟知しているため、適切な供花を選んで手配してくれます。
2.花屋に依頼する
地元の花屋に依頼する方法です。事前に葬儀社や会場に「持ち込みが可能か」「持ち込み料金が発生するか」を確認する必要があります。また、葬儀の形式や宗教に適した花の種類を伝え、適切な供花を準備してもらいましょう。
3.インターネットやFAXで注文する
近年では、インターネットやFAXで簡単に供花を注文できるサービスもあります。e-denpoなどのサービスを利用すれば、葬儀社との確認作業も代行してもらえるため安心です。ただし、注文は早めに行い、通夜や葬儀開始前に届くように手配しましょう。
供花の立札の書き方
供花に添える立札は、送り主を明確に伝える重要な役割を持っています。以下の形式を参考に記載してください。
1.個人名の場合:「〇〇家」「〇〇一同」など簡潔に記載します。
2.会社から送る場合:「会社名+代表者名」または「会社名+部署+一同」と記載します。会社名が長い場合は略しても問題ありません(例:「(株)〇〇」)。
3.連名で送る場合:連名で送る場合、立場や年齢順に右から左へ名前を並べるか、五十音順で記載します。人数が多い場合は「〇〇部一同」「〇〇有志一同」などとまとめて記載するのが無難です。
供花を送る際の注意点
供花を贈る際には、以下のポイントに注意することが大切です。
1. 派手すぎる花や香りの強い花を避ける
供花は葬儀の厳粛な雰囲気に合った花を選ぶことが基本です。赤や濃いピンクなど、祝い事を連想させる派手な色合いや、香りの強いユリやバラなどを大量に使用するのは避けましょう。白や淡い色を基調とした清楚な花を選び、他の参列者への配慮も忘れないようにしましょう。
2. 宗教や宗派に適した花を選ぶ
供花に使う花は、葬儀の宗教や宗派に応じて異なる場合があります。仏式や神式では白菊や百合、トルコキキョウなどが一般的ですが、キリスト教式では白やピンクの洋花(百合、カーネーションなど)が主流です。葬儀形式や故人の宗教に合わせて選ぶことが重要です。
3. サイズに配慮する
供花が大きすぎると、祭壇や会場のスペースに影響を与える場合があります。葬儀会場や祭壇の規模に応じて適切なサイズを選び、花屋や葬儀社と相談しながら手配を進めましょう。
4. 名前の記載を忘れない
供花には贈り主の名前を必ず記載しましょう。記載がない場合、遺族に「誰から贈られたものか分からない」と思われてしまいます。個人名や会社名、連名など、適切な形式で明記することがマナーです。
献花の流れ・作法
献花(けんか)は、故人への祈りや敬意を込めて花を捧げる厳粛な儀式です。特にキリスト教式の葬儀や追悼式で重要視される行為であり、静粛な態度と正しい作法を守ることが求められます。ここでは、献花の流れや注意点について詳しく解説します。
献花の基本的な手順
献花には、花の受け取りから祭壇に供えるまで、決められた持ち方や供え方があります。正しい手順を理解し、丁寧に行うことが大切です。
1. 花を受け取る
会場の係員から一輪の花を受け取ります。この際、右手で花の部分を持ち、左手で茎の根元を支えるのが基本的な持ち方です。丁寧に扱うことで、故人への敬意を表します。
2. 順番が来たら一礼
自分の順番が来たら、まず遺族に向かって一礼をします。その後、静かに祭壇の前へ進みます。行動中は静粛にし、周囲に配慮することが重要です。
3. 祭壇の前で花を供える
祭壇の前に着いたら、一礼をしてから花を供えます。花を供える際には、花の部分を自分の方に、茎の根元を祭壇側に向けて置きます。このとき、花を時計回りに90度回転させると、正しい向きで供えることができます。
4. 黙祷または礼拝
花を供えた後、黙祷や礼拝を行います。形式は宗教によって異なり、次のように行います:
・プロテスタント式:胸の前で手を組む。
・カトリック式:十字を切る。
・その他の参列者:手を合わせて黙祷を行う。
故人への祈りや感謝の気持ちを込めて、心静かに行うことが大切です。
5. 一礼して席に戻る
黙祷や礼拝が終わったら、祭壇に向かって一礼をします。その後、遺族や斎主にも一礼し、順路に従って静かに席に戻ります。
献花を行う際の注意点
献花は厳粛な儀式であるため、いくつかのマナーや注意点を守る必要があります。
1. 静かに行動する
葬儀場では静粛に行動し、周囲の雰囲気を乱さないようにしましょう。携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定しておくのがマナーです。また、列に並んでいる間や移動中に会話を控えることも重要です。
2. 花の正しい扱い方
花は茎を下に、花の部分を上に向けて供えるのが基本です。献花台の前で係員がいる場合は、指示に従い丁寧に供えます。また、花を捧げた後に持ち帰ることはマナー違反とされているため、必ずその場に供えたままにします。
まとめ
供花と献花は、故人への追悼や祈りを花で表す行為ですが、目的や形式に明確な違いがあります。供花は事前に手配し、祭壇を飾る贈り物として用いられます。一方、献花は式典中に一輪の花を手で捧げ、故人への祈りや敬意を示します。適切な手配方法やマナーを守ることで、厳粛な場での礼節をしっかりと示すことが大切です。
関連記事
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
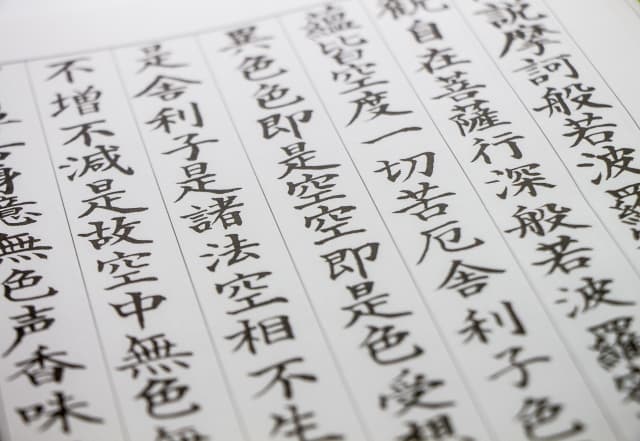
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
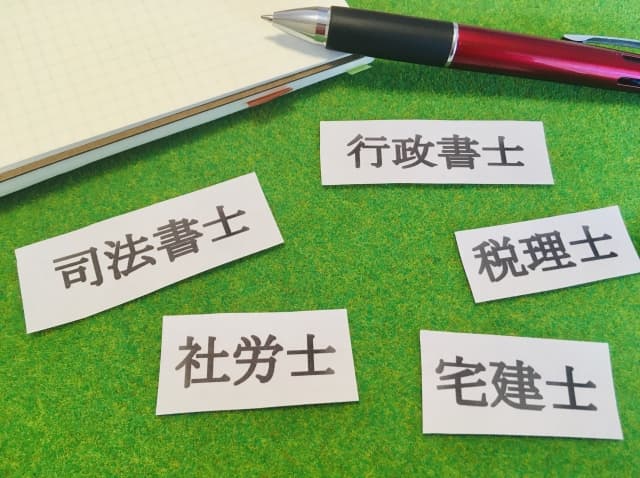
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説





