
県民共済で実現する経済的なお葬式|活用方法を徹底解説
公開日: 更新日:
人生の最後を飾る「お葬式」は、家族や親族、友人たちとの大切なお別れの場です。しかしながら、葬儀には多額の費用がかかるため、経済的な負担が遺族にのしかかることも少なくありません。
そんな中、注目されているのが「県民共済」を活用した葬儀の準備です。県民共済は、低価格な掛け金で手厚い保障を提供し、死亡保障金を葬儀費用に充てることができるため、経済的負担を軽減しつつ安心のセレモニーを実現します。
本記事では、県民共済を活用した葬儀の具体的な手順やメリット、さらには費用を抑える工夫など、幅広い情報を徹底的に解説します。葬儀の準備に悩んでいる方や、将来に備えたい方にとって、参考となる内容です。
県民共済とは?
県民共済は、日本全国の都道府県が運営する共済制度で、非営利組織によって提供されています。そのため、保険会社のように利益追求を目的とせず、加入者が相互扶助の精神で運営費用を支え合う仕組みとなっています。
県民共済の最大の特徴は、「低価格な掛け金で手厚い保障が受けられる」という点です。医療保障、災害保障、死亡保障など、幅広いリスクに対応しており、特に葬儀費用に活用できる死亡保障が注目されています。
具体的には、月々数千円程度という負担の少ない掛け金で、死亡時に数十万円から数百万円程度の保障が受け取れる仕組みです。また、持病があっても比較的加入しやすい点や、加入手続きが簡単である点も、多くの利用者に支持されています。
県民共済は都道府県ごとに運営されており、基本的な保障内容は共通していますが、各都道府県ごとに提供されるプランやサービス内容が若干異なります。これにより、地域に密着したサポートが可能となり、地域住民に寄り添ったサービスが展開されています。
県民共済のメリット
県民共済は、持病があっても比較的加入しやすい設計となっているのがメリットです。
診断書不要
他の保険と異なり、医師の診断書が不要です(健康状態に関する告知は必要)。
加入手続きが簡単
最小限の手続きでスムーズに加入できます。
(参照 https://money-career.com/article/1782 、https://cocozas.jp/coco-the-style/kenminkyosai-shinsakibishi/ )
加入可能年齢に注意
県民共済の加入可能年齢は0歳から69歳までです。そのため、早めに加入することで、長期間の保障を受けることができます。
(参照 https://www.hokepon.com/column/column-knowhow-031/ )
葬儀費用に県民共済を活用しよう
葬儀費用の相場
葬儀費用は一般的に高額で、全国平均では約100万円〜200万円とされています。この中には、通夜や告別式、火葬、斎場利用料、返礼品などの費用が含まれます。費用を抑えるためには、事前の計画やサービスの選択が非常に重要です。
県民共済の死亡保障
県民共済の死亡保障を活用することで、葬儀費用を大幅に軽減することができます。加入者が死亡した際には、年齢ごとの加入プランに応じて給付金が支給されます。例として「総合保障2型」と「熟年2型」の場合を見てみましょう。
「総合保障2型」(18歳〜59歳)
交通事故死亡:1,000万円
病気死亡:400万円
「熟年2型」(65歳〜69歳)
交通事故・不慮の事故死亡:200万円
病気死亡:100万円
県民共済には直接的な葬儀支援制度はありませんが、給付金の使途は受取人の判断に委ねられるため、この給付金を葬儀費用に充当することが可能です。
なお、県民共済の保障内容は年齢とともに変化し、特に70歳以降は保障額が減少していきます。
(参照 https://www.hokepon.com/column/column-knowhow-031/ )
葬儀費用などに活用する場合の内訳
死亡給付金は、葬儀費用以外にもさまざまな用途に活用することができますが、優先順位を明確にすることが重要です。以下は、死亡給付金の具体的な活用方法とその順番の一例です。
葬儀費用の補填
最優先で葬儀費用を支払います。家族葬や直葬であれば、県民共済の給付金内でほぼ全額を賄えるケースが多いです。
香典返しや法要費用
葬儀後に発生する香典返しや四十九日法要の準備費用も給付金でカバーします。
遺族の生活費として利用
残った給付金は、遺族の生活費や教育費として役立てることができます。特に、主たる収入者を失った場合には重要な資金となります。
その他の必要経費に充当
遺品整理費用や、行政手続きに伴う諸費用など、葬儀に関連する雑費を賄うことも可能です。
このように死亡給付金を適切に配分することで、葬儀にまつわるすべての経済的負担を軽減できます。
家族葬や直葬に給付金を活用
近年では、従来の一般葬ではなく、家族葬や直葬といったシンプルな葬儀形式を選ぶ人が増えています。これらの形式は費用を大幅に抑えることができ、県民共済の給付金範囲内でまかなえるケースも多くあります。
家族葬
親族やごく近い関係者のみが参列する葬儀形式。費用相場は30万円〜80万円。給付金の活用で、全額を賄うことも可能です。
直葬
通夜や告別式を行わず、火葬だけを行う葬儀形式。費用相場は15万円〜30万円。給付金だけで十分対応できます。
これらの形式を選ぶことで、故人や遺族の意向を尊重しつつ、費用を大幅に削減することが可能です。
死亡保障の給付金申請の流れ
県民共済を利用して葬儀の準備を進めるには、適切な手続きと必要書類を揃えることが重要です。以下は、死亡保障の給付金申請の主な流れです。
1. 死亡診断書の取得
医師が発行する死亡診断書を受け取ります。これが死亡給付金の申請や、火葬許可証の取得に必要となります。
2. 加入者証の準備
県民共済加入者には、加入時に発行される「加入者証」があります。この証書は、死亡給付金申請時に必須ですので、事前に保管場所を確認しておきましょう。
3. 給付金申請書の記入
県民共済窓口や公式サイトから給付金申請書を取得し、必要事項を記入します。記入ミスを防ぐため、申請書作成時は担当者に確認すると良いでしょう。
必要書類には、加入者・共済金受取人の戸籍謄本、住民票、共済金受取人の印鑑証明書も含まれます。
死因が不慮の事故(交通事故を含む)の場合は、被災証明書または事故証明書、事故状況報告書も必要です。
なお、共済金の請求は3年以内に行う必要があります。
(参照 https://money-career.com/article/2590 )
県民共済と一般的な葬儀保険の違い
県民共済は、給付金の使途は受取人の判断に委ねられる一方で、葬儀に特化した保障は提供していません。一般的な葬儀保険では、葬儀費用を直接カバーする保険商品が多いため、県民共済と組み合わせて利用することで、総合的な保障が得られます。
県民共済と葬儀保険を組み合わせて安心を強化
葬儀保険を追加で検討することで、以下のような利点が得られます。
葬儀費用を完全にカバー
葬儀保険で基本費用をカバーすることで、県民共済の給付金を追加費用に充当できます。
幅広い選択肢
葬儀保険には高齢者向けや短期契約型など多様な商品があるため、自分に合ったプランを選べます。
県民共済と組み合わせたい葬儀保険
県民共済だけではカバーしきれない場合に備え、葬儀専用の保険商品を組み合わせることで、さらに安心して準備ができます。以下のような保険商品を検討することがおすすめです。
葬儀保険(少額短期保険)
葬儀費用を目的とした特化型保険で、契約金額を葬儀代に充てられる仕組みです。掛け金は安価で、加入手続きも簡単な商品が多く、県民共済の死亡給付金と併用することで費用を完全にカバーできます。
終身保険
生涯にわたって保障が続くため、遺族が受け取れる保険金を葬儀費用として活用できます。終身保険は掛け金が比較的高めですが、資産運用の側面もあるため、安心感を高めたい方に適しています。
医療保険に付帯する死亡保障
一部の医療保険には死亡時の給付金が含まれている商品もあります。医療保障と葬儀費用の両方を準備できるため、効率的にリスクに備えることが可能です。
こうした商品を組み合わせることで、予想外の費用にも柔軟に対応でき、遺族への経済的負担を大きく軽減できます。
長期的な費用計画の立て方
葬儀費用を完全に備えるためには、短期的な準備だけでなく、長期的なライフプランの中で計画を立てることが重要です。以下のステップで費用計画を進めると良いでしょう。
必要な費用の総額を把握
自分や家族が希望する葬儀の形式や規模を基に、大まかな費用をシミュレーションします。
共済や保険のプランを組み合わせる
県民共済の給付金に加え、葬儀保険を組み合わせ、予算のギャップを埋める計画を立てます。
事前相談を活用する
葬儀社や保険会社に事前相談を行い、具体的な費用や必要な準備を確認します。
ライフイベントに応じて見直す
家族構成や収入状況の変化に応じて、保障内容を定期的に見直し、最適なプランを維持します。
長期的な視点で計画を立てることで、突然の不幸に直面しても焦らず対応できる備えが整います。
よくあるQ&A
Q. 家族で県民共済に加入するメリットは?
A. 家族で県民共済に加入することで、次のようなメリットが得られます。
家族全員が保障を受けられる
各メンバーが個別に死亡保障を持つことで、どのような不幸にも柔軟に対応できます。
掛け金がリーズナブル
県民共済の掛け金は非常に低価格で、家族全員が加入しても家計への負担が少なく済みます。
Q. 県民共済を解約した後の保障はどうなる?
A. 県民共済を解約した場合、保障はその時点で終了します。したがって、以下のような点に注意が必要です。
保障の移行先を検討
解約後の保障がなくなるため、必要に応じて他の保険商品に切り替える準備を行いましょう。
葬儀費用の備えがあるか確認
解約しても葬儀費用を用意できるかどうかを確認し、不足している場合は早めに対応策を講じることが重要です。
割戻金の受け取り
県民共済を解約しても、事業年度末時点で加入していれば、その年度の割戻金を受け取ることができます。
再加入の制限
解約後、年齢によっては再加入できない可能性があります。特に69歳以降は新規加入ができないため注意が必要です。
都道府県間の移動
転居により都道府県が変わる場合、解約ではなく移管手続きを行うことで保障を継続できます。
県民共済の解約を検討する際は、これらの点を十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。
(参照 https://money-career.com/article/2582)
まとめ
県民共済は、葬儀費用の負担を軽減しつつ、家族が安心して送り出せる環境を整えるために非常に有効な選択肢です。死亡給付金を上手に活用することで、葬儀費用だけでなく遺族の生活費や法要費用もカバーすることが可能です。
さらに、共済だけでなく葬儀保険や終身保険を組み合わせることで、さらに手厚い備えができ、万が一に備える安心感を強化できます。ぜひ本記事を参考に、県民共済を活用した最適な葬儀準備を進めてください。
最後に、迷ったときや不安を感じたときは、県民共済の窓口に相談することで、プロのアドバイスを受けることができます。家族のためにも、早めの準備を始めてみてはいかがでしょうか。
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
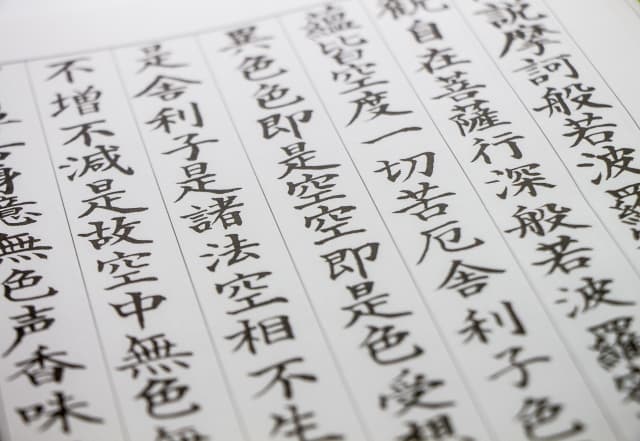
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
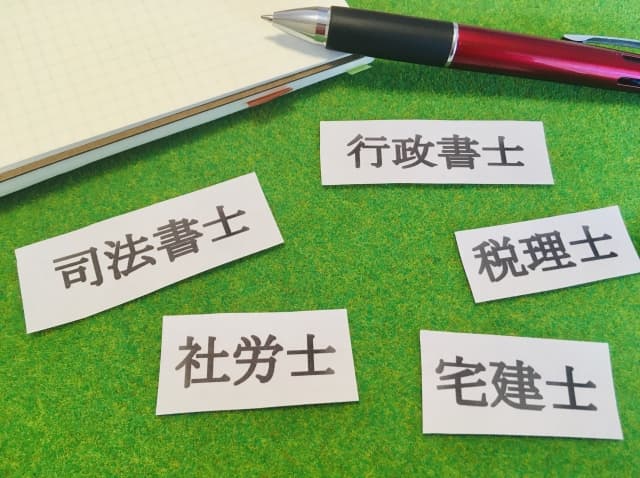
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説




