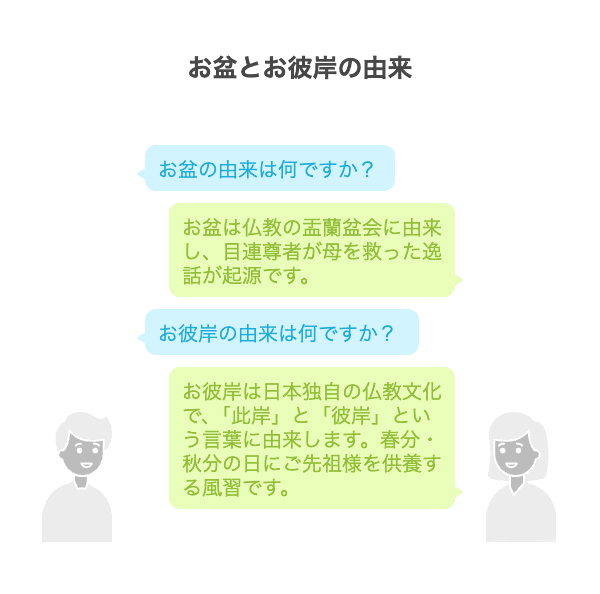期間・目的・供養の違いが一目でわかる|お盆とお彼岸をきちんと理解してご先祖様を大切に供養するための基礎知識
公開日:
はじめに|「お盆とお彼岸って何が違うの?」と聞かれたら
「お盆とお彼岸って同じような行事だよね」と思っている方は少なくありません。しかし、実際には目的や意味、そして時期において大きな違いがあります。
たとえば、ご家族やお子さんに「お盆とお彼岸はどう違うの?」と聞かれたとき、うまく答えられなかった経験はありませんか。多くの人が漠然とした理解のまま過ごしており、いざ説明を求められると困ってしまうこともあるでしょう。
この記事では、お盆とお彼岸の違いを「意味」「時期」「供養の内容」という3つの観点から整理して解説していきます。由来や歴史にまで遡って知識を深めることで、ただ形式的に行事をこなすのではなく、心を込めてご先祖様を供養できるようになります。
両者の違いをきちんと理解することは、仏事を受け継ぎ、家族や地域の伝統を次世代に伝えるうえでも大切です。ここから順に、比較表や具体的な事例を交えながら詳しく見ていきましょう。
お盆とお彼岸の基本的な違いとは
お盆とお彼岸は、いずれもご先祖様を供養する仏教行事ですが、その性格や意味合いにははっきりとした違いがあります。ここでは、まず全体像をつかみやすいように、目的・時期・行事内容・お供え物といった要素を一覧表にまとめます。
項目 | お盆 | お彼岸 |
目的 | ご先祖様をお迎えして感謝を伝え、供養する | ご先祖様を供養し、自らも修行を実践する |
時期 | 毎年7月または8月の13日〜16日(地域差あり) | 春分・秋分の日を中心とした7日間(年2回) |
行事内容 | 精霊棚の設置、迎え火・送り火、盆踊り、法要 | 墓参り、仏壇へのお供え、六波羅蜜の実践 |
お供え物 | 精霊馬(きゅうりやなす)、盆団子、ほおずき | おはぎ(春)・ぼたもち(秋)、落ち着いた色合いの花 |
宗教的意味 | 盂蘭盆会(うらぼんえ)が起源 | 此岸と彼岸の架け橋としての仏教行事 |
この表からもわかるように、どちらも「ご先祖様を偲ぶ」という共通点はあるものの、焦点の当て方が異なります。
特に大きな違いは「ご先祖様が帰ってくる」という考え方です。お盆は、ご先祖様の霊がこの世に戻ってくるとされ、それを迎え入れて供養する行事です。一方、お彼岸は霊が帰ってくるというよりも、生きている私たちがご先祖様に思いを馳せ、供養と自己修養を行う期間とされています。
また、仏教行事としての位置づけにも違いがあります。お盆はインドや中国から伝わった盂蘭盆会に由来し、日本独自の風習と融合して発展しました。一方、お彼岸は「太陽が真西に沈む春分・秋分の日」を中心に据えた、日本独自の仏教文化です。
このように、似ているようで実は性格が異なるお盆とお彼岸。次に、その由来と歴史を詳しく見ていきましょう。
期間の違いと行われること
お盆の期間と地域差
お盆は一般的に毎年8月13日から16日の4日間に行われますが、地域によっては7月に行う「新暦盆(7月盆)」と、8月に行う「旧暦盆(8月盆)」があります。
・7月盆:主に東京や関東の一部で行われる。新暦の7月13日〜16日に実施。
・8月盆:全国的に広く行われている。旧暦の7月15日前後を新暦に換算した8月13日〜16日が中心。
この違いは、暦の採用に由来しています。明治時代に日本が太陽暦を導入した際、従来の旧暦に基づく行事を新暦に合わせた地域と、旧暦に近い8月にずらして続けた地域があったためです。
また、お盆の中でも特別な意味を持つのが「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん)」です。これは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆を指し、特に丁寧に法要が営まれます。僧侶を招いて読経をお願いしたり、親族や知人を招待して供養を行ったりするなど、通常のお盆よりも大規模になることが多いです。
お彼岸の期間と年2回の理由
お彼岸は年に2回、春分と秋分の日を中日として、その前後3日を加えた7日間に行われます。
・春のお彼岸:3月の春分の日を中心にした7日間
・秋のお彼岸:9月の秋分の日を中心にした7日間
合計で年間14日間が「お彼岸」とされます。
なぜ年に2回行うのかというと、春分・秋分の日は太陽が真西に沈むため、西方極楽浄土を象徴的に感じやすいからです。また、農耕社会だった日本では、春のお彼岸は豊作を祈り、秋のお彼岸は収穫を感謝する意味も込められていました。こうした生活文化と仏教的信仰が結びつき、全国的に定着していったのです。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉の通り、季節の移ろいを実感できる節目であることも、人々が自然に先祖を偲びやすい背景となっています。
目的の違いを理解する
お盆の目的は「ご先祖様を迎えて供養する」
お盆は、ご先祖様の霊が現世に戻ってくるとされ、その霊を迎えて供養することが中心的な目的です。日本の家庭では、お盆になると仏壇や精霊棚(しょうりょうだな)を整え、迎え火を焚いてご先祖様の霊をお迎えします。
迎え火には、玄関先や庭先で麻の茎やおがらを燃やす風習があり、「こちらですよ」と霊が迷わず帰ってこられるよう道を照らす意味があります。帰ってきたご先祖様には、精霊馬(きゅうりやなすで作った馬や牛)を用意し、「馬で早く来て牛でゆっくり帰る」という願いを込めます。
さらに、家族が集まり、感謝の気持ちを伝えることも大切なお盆の目的です。親戚一同が顔を合わせる機会にもなり、単に宗教的な行事にとどまらず、家族の絆を深める場としての役割も果たしています。最後には送り火を焚いて、ご先祖様の霊を見送ります。これら一連の流れが、お盆の供養の中心です。
お彼岸の目的は「ご先祖様の供養と自らの修行」
一方、お彼岸は「ご先祖様の供養」と同時に「自分自身の仏道修行」が大きな目的です。ご先祖様を偲ぶ気持ちはもちろんですが、それ以上に、六波羅蜜(ろくはらみつ)と呼ばれる六つの修行を実践する期間とされています。
六波羅蜜とは以下の6つを指します。
- 布施(ふせ):他人に施しをすること
- 持戒(じかい):戒律を守り正しい生活をすること
- 忍辱(にんにく):辛抱強く耐えること
- 精進(しょうじん):怠けず努力すること
- 禅定(ぜんじょう):心を静めて集中すること
- 智慧(ちえ):真理を見抜く知恵を養うこと
この六波羅蜜を実践することによって、現世(此岸)から悟りの世界(彼岸)へと近づけると考えられてきました。
そのため、お彼岸には墓参りをしてご先祖様に感謝を伝えると同時に、自らの心を整える時間としても大切にされてきたのです。宗派を問わず全国的に広く行われているのは、このように「供養」と「修行」の両方を兼ね備えた行事だからといえるでしょう。
お供えものや花の違いはある?
お盆に用意するもの
お盆では、ご先祖様が現世に戻ってきたときに喜んでもらえるよう、さまざまなお供え物を準備します。代表的なものは次の通りです。
- 精霊馬(しょうりょううま)
きゅうりやなすに割り箸を刺して作る馬や牛。馬には「早く来てもらう」、牛には「ゆっくり帰ってもらう」という願いが込められています。 - 盆団子
小さな団子を精霊棚に供える風習があります。これは、ご先祖様が旅の途中で口にする食べ物とされます。 - ほおずき
赤い提灯のような形をしているため、ご先祖様が迷わないよう道しるべとして供えられます。 - 野菜や果物
季節の恵みを供えることで、自然の恵みに感謝し、ご先祖様にもその喜びを分け合う意味があります。
お盆は「おもてなし」の要素が強く、食べ物や飾りに華やかさがあるのが特徴です。
お彼岸に用意するもの
お彼岸のお供え物は、お盆に比べると落ち着いた雰囲気が特徴です。
- おはぎ(春)とぼたもち(秋)
春のお彼岸では「おはぎ」、秋のお彼岸では「ぼたもち」を供える風習があります。
両者の違いは、使う花の名前に由来しています。春は牡丹(ぼたん)にちなんで「ぼたもち」、秋は萩(はぎ)にちなんで「おはぎ」と呼ばれます。 - 落ち着いた色合いの花
お彼岸には菊やリンドウ、カーネーションなど、控えめで落ち着いた色合いの花が選ばれることが多いです。
これは、ご先祖様を静かに偲び、感謝の気持ちを表すためといわれています。 - 線香や果物
香りの良い線香を供えることも一般的で、果物などの季節の食べ物も添えられます。
このように、お盆のお供えは「ご先祖様を歓迎するおもてなし」、お彼岸のお供えは「ご先祖様を偲び、心を落ち着ける」という違いがあります。
お墓参りや法要の違いと共通点
お盆とお彼岸のいずれでも、お墓参りや法要は欠かせない大切な行いです。しかし、その意味合いには微妙な違いがあります。
お盆のお墓参りと法要
お盆は「ご先祖様を迎える」行事であるため、墓参りの際には霊を迎える意味合いが強くなります。迎え火や送り火を焚くのも、そのためです。
家族や親戚が集まり、お墓を掃除して花や線香を供え、精霊棚にご先祖様をお迎えします。特に初盆や新盆では僧侶を招いて読経をお願いし、丁寧な供養を行うのが一般的です。
お彼岸のお墓参りと法要
お彼岸では、ご先祖様の霊が帰ってくるという考え方よりも、こちらからご先祖様に心を寄せるという意味合いが強くなります。そのため、墓参りは「日常の中で感謝の心を忘れない」ことを実践する象徴とされています。
また、お彼岸は六波羅蜜の修行期間でもあるため、墓参りだけでなく、写経や読経などを通じて自分自身の心を整える人もいます。
共通点
両者に共通しているのは「お墓を掃除して清め、ご先祖様に感謝を伝える」ことです。掃除には単なる清潔さを保つだけでなく、心を込めてご先祖様を敬うという意味が込められています。
つまり、お盆は「ご先祖様をお迎えして過ごす特別な時間」、お彼岸は「日常生活の中で心を整え、ご先祖様を想う時間」と位置づけられるのです。
よくある疑問と回答
Q. お盆とお彼岸、どちらが大事?
結論からいえば、どちらも同じくらい大切です。お盆は「ご先祖様を迎えて感謝を伝える特別な行事」、お彼岸は「日常の中でご先祖様を偲び、心を整える行事」と、それぞれ役割が異なります。どちらが優先されるというものではなく、いずれも大切に受け継がれてきた意味ある行事です。
Q. 両方とも何かしないといけないの?
必ずしも形式的に全てを行う必要はありません。大切なのは「ご先祖様に心を向けること」です。時間が取れなければ仏壇に手を合わせるだけでも良いですし、可能であれば墓参りやお供えをするとさらに丁寧な供養になります。大切なのは気持ちであり、形にとらわれすぎないことです。
Q. お彼岸に亡くなる人が多いって本当?
昔から「お彼岸はあの世とこの世が近づく時期だから亡くなる人が多い」といわれることがあります。実際に統計的な裏付けはありませんが、季節の変わり目で体調を崩しやすいことや、気温差による健康リスクが関係していると考えられます。宗教的な意味だけでなく、生活習慣や医学的な側面も影響していると理解するとよいでしょう。
Q. 子どもにどう説明すればよい?
子どもには難しい仏教用語を使うのではなく、「お盆はご先祖様が帰ってきてくれる日」「お彼岸はご先祖様を思い出してありがとうを伝える日」と、シンプルに説明するのがおすすめです。精霊馬やおはぎなど、具体的なお供えを一緒に準備することで、自然と意味を理解しやすくなります。
このように、疑問を解消しながら理解を深めることで、お盆やお彼岸をより身近に感じられるようになるでしょう。
形式だけじゃなく“心を込める”ために
お盆やお彼岸を迎えると、多くの人が「とりあえず毎年やっているから」と形式的に準備を進めがちです。しかし、これらの行事の本質は、形よりも「心」にあります。
意味を知ってから行う供養は、ただの習慣的な行事とは違った深みを持ちます。ご先祖様を迎え、感謝を伝えることは、自分自身のルーツを見つめ直し、今ある命のつながりを感じる大切な機会となります。
また、将来的に自分が仏事を受け継ぐ立場になったとき、行事の意味を理解していれば迷わずに準備ができます。親や祖父母に任せきりにせず、自分がその役割を果たせるよう備えておくことは、家族を守る大切な一歩です。
さらに、お盆やお彼岸を子どもや孫に伝えていくことは、家族や次世代への橋渡しにもなります。供養を通して「ありがとうの気持ちを伝える大切さ」を共有することは、仏事の枠を超えて、家庭教育や心の豊かさにもつながります。
形式だけにとらわれず、心を込めてご先祖様と向き合うこと。それが、お盆やお彼岸を現代に生かす大切な姿勢といえるでしょう。
まとめ
お盆とお彼岸は、どちらもご先祖様を供養する大切な仏事ですが、その目的・時期・行うことには明確な違いがあります。
- お盆は、毎年7月または8月に行われ、ご先祖様を迎えて感謝を伝える行事。迎え火や送り火、精霊棚の準備など「おもてなし」の意味合いが強い。
- お彼岸は、春分・秋分を中心に年2回行われ、ご先祖様を偲ぶと同時に、自らも六波羅蜜を実践し心を整える行事。墓参りや静かな供養が中心。
- お供え物や花も異なり、お盆は精霊馬や盆団子、華やかな飾りが多く、お彼岸はおはぎ・ぼたもちや落ち着いた花が選ばれる。
迷ったときは、「ご先祖様に心を向ける」ことが最も大切だと覚えておくとよいでしょう。形式にとらわれすぎる必要はなく、仏壇に手を合わせたり、お墓を掃除してお参りしたりするだけでも十分に意味があります。
お盆とお彼岸は単なる年中行事ではなく、家族の絆を深め、世代を超えて感謝の心を伝える貴重な機会です。今年からは、意味を理解したうえで丁寧に供養を行い、ご先祖様と心でつながるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
参考記事
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

大祓(おおはらえ)とは?意味・由来・時期・作法をわかりやすく解説|夏越の祓との違いや人形の使い方も紹介

灯明供養とは?初心者でもできるやり方と準備すべきもの

涅槃会(ねはんえ)とは?意味・由来・開催時期と行事内容をわかりやすく解説|お釈迦様の命日に行われる供養の法要

ペットのお盆供養は人と同じでいいの?違いや準備、初盆の迎え方をやさしく解説

法事での「のし袋」完全マニュアル:購入先、選び方、書き方からマナーまで徹底解説!

法事のお金に関する完全ガイド|香典・お布施・諸経費の内訳と準備方法

法事は平日でも失礼にならない!押さえておきたい注意点と実践方法

失敗しない法事の服装選び!基本マナーとポイントを徹底解説