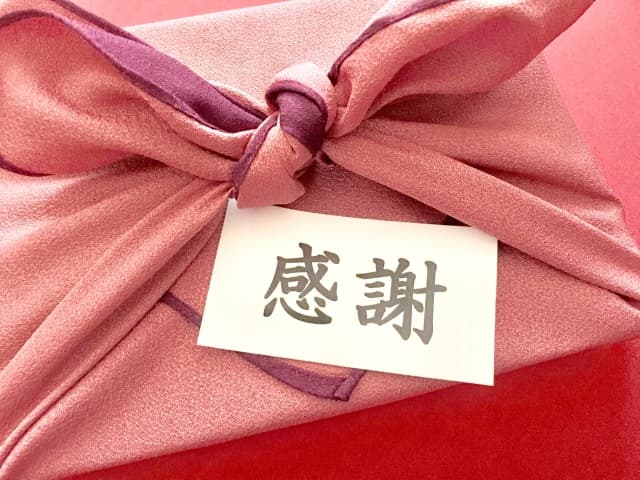
香典返しのお礼状とは?適切な書き方とマナー、文例を解説
公開日: 更新日:
香典返しのお礼状は、故人を偲んで香典をくださった方々へ感謝の気持ちを伝える大切な役割を果たします。お礼状を適切に書くことで、喪主や遺族の気持ちを表し、今後の良好な関係を保つことにもつながります。しかし、香典返しのお礼状には独自のマナーがあり、形式や表現に迷う方も多いでしょう。
本記事では、香典返しのお礼状の基本知識から、書き方のポイント、マナー、具体的な文例まで詳しく解説します。さらに、香典返しを受け取った側のお礼の仕方や、お礼状を簡単に作成する方法についても触れていきます。
香典返しのお礼状を準備する際の参考にしていただき、感謝の気持ちを適切に伝えられるようお手伝いできれば幸いです。
香典返しのお礼状とは?目的と役割
香典返しのお礼状は、故人を偲んで香典をくださった方々への感謝の気持ちを表すための手紙です。単なるお礼の言葉だけでなく、忌明け(四十九日法要)を迎えたことの報告や、故人の生前のご厚情への感謝も含まれます。
香典返しの品とともに送るのが一般的で、直接手渡しする場合は口頭でお礼を伝えれば良いとされていますが、郵送の場合は必ずお礼状を添えるのがマナーです。また、お礼状は単なる儀礼的なものではなく、相手への心遣いを示すものでもあるため、丁寧な言葉遣いと適切な形式を守ることが大切です。
お礼状が必要なケース
・香典返しを郵送する場合
・直接お会いしてお礼を伝える機会がない場合
・会社や団体などから香典を受け取った場合
・遠方の方や、あまり親しくない方から香典をいただいた場合
お礼状が不要なケース
・直接香典返しを渡し、お礼を伝えた場合
・すでに葬儀の場でお礼を述べた場合
・家族や親族など、日常的に交流がある相手
ただし、どんな場合でも「感謝の気持ちを伝える」ことが大切です。不要とされるケースでも、簡単なメッセージや口頭でのお礼を忘れないようにしましょう。
香典返しのお礼状の書き方
お礼状の基本構成
・頭語と結語(例:「拝啓」〜「敬具」)
・香典への感謝の言葉
・故人の報告と忌明けのご挨拶
・香典返しの品についての説明
・相手への気遣いと今後のお願い
・結びの言葉
これらの要素をバランスよく含めることで、以下のように適切な香典返しのお礼状を作成できます。
一般的な例文(シンプルな書き方)
拝啓
このたびは、亡○○(故人名)の葬儀に際しまして、ご厚志を賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで、○月○日に滞りなく四十九日の法要を執り行うことができました。
ささやかではございますが、心ばかりの品をお送りさせていただきましたので、ご受納いただければ幸いです。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら、書中にて御礼申し上げます。
敬具
頭語と結語の使い方
お礼状では、基本的に「拝啓」から始め、「敬具」で締めくくるのが一般的です。ただし、格式を重視する場合は「謹啓」〜「謹白」や「謹言」などを使うこともあります。
また、カジュアルな関係の方には、頭語・結語を省略し、シンプルに感謝の言葉から始めることも可能です。ただし、ビジネス関係者や目上の方に送る場合は、正式な書き方を守りましょう。
香典への感謝の言葉
香典をいただいたことへの感謝を伝える部分では、以下のような表現が適しています。
「このたびのご厚志に深く感謝申し上げます。」
「お心のこもったご厚志を賜り、誠にありがとうございました。」
「ご丁寧なお心遣いをいただき、心よりお礼申し上げます。」
故人の報告と忌明けのご挨拶
香典返しのお礼状では、忌明け(四十九日法要)が済んだことを報告します。
例文
「おかげさまで、○○の四十九日法要を滞りなく相済ませました。」
また、故人が生前お世話になったことへの感謝も添えると、より丁寧な印象になります。
香典返しの品についての説明
お礼状では、香典返しの品をお送りしたことを伝えるのも重要です。ただし、「つまらないものですが」という表現は避け、「心ばかりの品ですが」とするのが一般的です。
例文
「心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納いただければ幸いです。」
「ささやかではございますが、感謝のしるしとしてお納めいただきたく存じます。」
このように、丁寧な表現を用いることで、相手に失礼のない文章になります。
相手への気遣いと今後のお願い
香典返しのお礼状では、相手の健康や今後の関係についても触れると、より温かみのある内容になります。
例文
「時節柄、くれぐれもご自愛ください。」
「今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。」
ビジネス関係者などには、「ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます」という表現を加えても良いでしょう。
結びの言葉
最後に、再度感謝の気持ちを述べ、結びの言葉で締めくくります。
例文
「略儀ながら書中にて御礼申し上げます。」
「まずは書中をもちまして御礼申し上げます。」
お礼状の最後は、シンプルかつ丁寧にまとめるのがポイントです。
お礼状を書く際のマナーと注意点
句読点を使わない理由
香典返しのお礼状では、「、」や「。」の句読点を使わないのが一般的なマナーとされてきました。これは、弔事において「区切りをつけない」=「悲しみを断ち切らない」という意味を持つためです。
しかしこれまでに紹介したように、最近では読みやすさを重視して句読点を使うお礼状も一般的になりつつあります。特に若い世代や親しい関係の方へのお礼状では、自然な文章にするために句読点を使うことが多いでしょう。
例:句読点を使わない文
「このたびは過分なるご厚志を賜り厚く御礼申し上げます 先日四十九日の法要を滞りなく相済ませましたので心ばかりの品をお送りいたしました 何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます」
例:句読点を使う文
「このたびは、過分なるご厚志を賜り、厚く御礼申し上げます。先日、四十九日の法要を滞りなく相済ませましたので、心ばかりの品をお送りいたしました。何卒、ご受納くださいますようお願い申し上げます。」
格式を重んじる場合や年配の方へのお礼状では、句読点を使わずに書くのが無難です。ただし、親しい間柄や読みやすさを優先したい場合は、句読点を使っても問題ありません。状況に応じて柔軟に対応しましょう。
忌み言葉・重ね言葉を避ける
弔事では、不幸が続くことを連想させる「忌み言葉」や「重ね言葉」を使わないようにするのがマナーです。
避けるべき表現と適切な言い換え例
忌み言葉・重ね言葉 | 適切な言い換え |
|---|---|
繰り返し、重ね重ね | 深く、誠に |
再び、続く、続けて | このたび |
追って、引き続き | さきに、改めて |
忙しい | お忙しいところを |
亡くなる、死ぬ | 死去 |
例えば、「重ね重ねお礼申し上げます」という表現は避け、「心より感謝申し上げます」に言い換えると良いでしょう。
適切な用紙・封筒の選び方
香典返しのお礼状には、正式なマナーとして奉書紙や白無地の便箋を使用するのが一般的です。
適切な用紙・封筒の種類
奉書紙(正式):格式のある和紙で、目上の方や会社関係者向け
白無地の便箋(カジュアル):親しい人や友人向け
カード・ハガキ:簡易的なお礼状として利用可能
また、封筒も白無地のものを使用し、郵送する場合は二重封筒を避ける(不幸が重なることを連想させるため)ようにします。
手書きと印刷のどちらが良い?
お礼状は手書きが最も丁寧とされていますが、香典返しの件数が多い場合などは、印刷されたお礼状を使うことも問題ありません。
手書きのメリット
・より気持ちが伝わりやすい
・目上の方や親しい人へのお礼状に適している
印刷のメリット
・多くの人に送る場合に効率的
・企業・団体宛てには印刷が一般的
手書きの場合は、毛筆や筆ペンを使用し、楷書体で丁寧に書くと良いでしょう。
お礼状を送る適切な時期とタイミング
香典返しのお礼状は、忌明け(四十九日)を過ぎた後、1ヶ月以内に送るのが一般的です。
お礼状が遅れた場合は、「ご挨拶が遅くなりましたが」といったお詫びの一文を添えると良いでしょう。
お礼状の文例集|ケース別
香典返しのお礼状の文面は、送り先の関係性や宗教、シチュエーションによって適切な表現を使い分ける必要があります。以下に、ケースごとの例文を紹介します。
親しい方へのお礼状(友人・親族向け)
親愛なる○○様へ
このたびは、○○(故人名)のために温かいお心遣いをいただき、本当にありがとうございました。
おかげさまで、○月○日に四十九日の法要を無事に終えることができました。
生前○○も、○○様とのご縁を大変大切にしておりました。
ささやかではありますが、心ばかりの品をお送りいたしますので、どうぞお納めください。
これからも変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
会社関係・上司へのお礼状
拝啓
このたびは、故○○の葬儀に際しまして、ご丁寧なお心遣いを賜り誠にありがとうございました。
○月○日に無事に四十九日法要を執り行い、滞りなく忌明けを迎えることができました。
皆様のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
ささやかではございますが、香典返しの品をお送りいたしますので、ご受納いただければ幸いです。
まずは略儀ながら、書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
遠方の方・お付き合いの少ない方への例文
拝啓
このたびは、○○(故人名)のためにご厚志を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで、○月○日に四十九日法要を無事に終えましたことをご報告申し上げます。
遠方にお住まいのため、直接ご挨拶が叶いませんが、書中をもちまして御礼申し上げます。
なお、心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご受納いただければ幸いです。
敬具
連名で香典をいただいた場合のお礼状
拝啓
このたびは、故○○の葬儀に際しまして、○○様をはじめ皆様よりご芳志を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで、○月○日に四十九日法要を滞りなく執り行うことができました。
ささやかではございますが、感謝のしるしとして、心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご受納ください。
まずは略儀ながら、書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
香典返しのお礼状を送る方法と注意点
香典返しのお礼状を送る際には、適切な方法とマナーを守ることが大切です。特に、郵送する場合のマナーや、手渡しと郵送の使い分け、返信の必要性など、さまざまな注意点があります。ここでは、香典返しのお礼状の送付方法について詳しく解説します。
手渡し・郵送どちらが適切?
香典返しのお礼状は、状況に応じて「手渡し」か「郵送」のどちらかを選びます。
手渡しの場合のポイント
・直接会った際に、「このたびはありがとうございました」と感謝を述べながら渡す。
・お礼状がなくても口頭でしっかりお礼を伝えれば問題なし。
郵送の場合のポイント
・香典返しの品とともに、お礼状を同封する。
・適切な封筒や便箋を使用し、丁寧に書くことを心掛ける。
・香典返しの品を業者から直送する場合でも、お礼状は同封するのがマナー。
郵送する際のマナー(封筒・切手・宛名の書き方)
香典返しのお礼状を郵送する場合、封筒・切手・宛名の書き方にも注意が必要です。
封筒の選び方
・白無地の封筒を使用(派手な装飾のある封筒は避ける)。
・二重封筒は避ける(不幸が重なることを連想させるため)。
・便箋1枚で収める場合は、封筒に入れず折らずに同封してもOK。
切手の選び方
・通常の切手でOKだが、弔事用の切手(菊のデザインなど)を使うとより丁寧。
・料金不足にならないよう、封筒の重さを確認する。
宛名の書き方
・目上の方には「様」、企業宛の場合は「御中」をつける。
・会社関係者には、フルネーム+「様」と書くのが丁寧。
メールやLINEでのお礼状はOK?
近年、メールやLINEでのお礼も増えていますが、香典返しの場合は基本的に手紙が望ましいとされています。しかし、遠方の方や親しい間柄であれば、メールやLINEでお礼を伝えるのも許容されています。
メールでのお礼の例文
件名:先日はありがとうございました
○○様
このたびは、故○○の葬儀に際しまして、ご厚志を賜り誠にありがとうございました。
先日、四十九日法要を無事に終えましたことをご報告申し上げます。
感謝の気持ちを込めまして、心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納いただければ幸いです。
今後とも変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
○○(喪主の名前)
LINEの場合
○○さん
このたびは香典をいただき、本当にありがとうございました。
無事に四十九日を迎えることができましたので、心ばかりの品をお送りします。
また改めてお会いできる日を楽しみにしています。
香典返し不要と伝えられた場合の対応方法
香典返しは日本の弔事マナーの一環ですが、相手によっては「お返しは不要」と伝えられることがあります。この場合の対応として、以下の選択肢があります。
それでもお礼状だけは送る
香典返しを辞退されても、感謝の気持ちを伝えるためにお礼状だけは送るのがマナーです。
お礼状のみ送る場合の例文
拝啓
このたびは、故○○の葬儀に際しまして、ご厚志を賜り誠にありがとうございました。
お心遣いに深く感謝申し上げます。
末筆ながら、貴殿のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
敬具
寄付をする(香典返しの代わり)
相手が「お返し不要」と言っていても、故人の名義で寄付をするという方法もあります。その場合、お礼状に寄付の報告を記載すると良いでしょう。
寄付を報告する場合の例文
拝啓
このたびは、○○(故人名)のためにご厚志を賜り、誠にありがとうございました。
感謝の気持ちを込め、○○基金へ寄付させていただきましたことをご報告申し上げます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
香典返しのお礼状を簡単に作成する方法
香典返しのお礼状を作成する際には、適切な文章を考えるだけでなく、書式やマナーにも注意を払う必要があります。しかし、忙しい中で一から作成するのは大変な作業です。そこで、お礼状を簡単に作成するための便利な方法を紹介します。
テンプレートを活用して作成する
香典返しのお礼状には、決まった形式があるため、テンプレートを活用することで効率的に作成できます。
テンプレートを使うメリット
・文章の構成やマナーを守ったお礼状が作れる
・何枚も作成する際に統一感が出る
・時間を節約できる
おすすめのテンプレートの種類
・無料ダウンロード可能なWord・PDFテンプレート(インターネット上で入手可能)
・香典返し業者が提供する挨拶状テンプレート(ギフト会社が提供)
・手書き用の例文集(文例を参考に自分でアレンジ)
テンプレートを利用する際は、個別に相手の名前や送り主の情報を記入することで、機械的な印象を避けることができます。
お礼状作成サービスを利用するメリット
最近では、香典返しのギフト業者や専門のサービスを利用して、お礼状を作成・印刷してもらうことができます。
メリット
・プロが適切な文面を作成(失礼のない文章になる)
・印刷された美しい仕上がり(手書きが苦手な方におすすめ)
・香典返しの品とセットで送れる(手間を省ける)
主なサービス提供会社
・百貨店の香典返しギフトサービス
・葬儀会社の返礼品サービス
・ネット通販の香典返し専門店
特に、香典返しのギフトに無料でお礼状が付いてくるサービスもあるため、活用すると良いでしょう。
お礼状付きの香典返しギフトサービスとは?
香典返しのギフトを専門業者に依頼すると、お礼状を同封するサービスが用意されていることが多いです。
このサービスの特徴
・テンプレートから選んで簡単に作成可能
・送り先ごとにカスタマイズできる(個別の名前を入れられる)
・香典返しの品と一緒に送れるので手間がかからない
利用方法
1. ギフト会社のサイトで香典返しを選ぶ
2. お礼状のテンプレートを選択
3. 必要な情報を入力(故人の名前・日付・送り主の名前など)
4. 業者が印刷・同封して発送
忙しい方や、お礼状を作るのが難しい方には、非常に便利な方法です。
100均や文具店で揃えられるお礼状の便箋・封筒
手書きでお礼状を作成する場合、100均や文具店で必要な道具を揃えることができます。
おすすめのアイテム
・奉書紙や和紙の便箋(格式を重んじる方へ)
・白無地の封筒(二重封筒は避ける)
・薄墨の筆ペン(香典返しにふさわしい筆記具)
特に、最近では100円ショップでも、弔事用の便箋や封筒が手に入るため、気軽に準備できます。
香典返しを受け取った側のお礼の仕方
香典返しは本来、香典を受け取った側が感謝の気持ちを込めて贈るものです。そのため、香典返しを受け取った側は、基本的に改めてお礼を伝える必要はないとされています。しかし、場合によっては、お礼を伝えた方が良いケースもあります。
ここでは、香典返しを受け取った際のお礼の仕方について、適切な対応方法を解説します。
香典返しをいただいたらお礼は必要?
香典返しを受け取った側の対応は、ケースによって異なります。
お礼が不要なケース
・香典返しに添えられたお礼状で、感謝の気持ちが伝わっている場合
・形式的なやり取りを重視しない間柄(親しい友人や親族など)
・会社の同僚や部下から香典返しを受け取った場合
基本的には、香典返しを受け取った時点で一連の弔事のやり取りは終了します。そのため、追加でお礼を伝える必要はありません。
お礼を伝えた方が良いケース
・手書きの丁寧なお礼状が添えられていた場合
・直接渡された場合(その場でお礼を伝えるのがマナー)
・目上の方や会社の上司・取引先から香典返しを受け取った場合
・特別にお世話になった故人のご家族から受け取った場合
このようなケースでは、お礼を伝えることで相手に対する敬意を示せます。
手紙・はがきでお礼を伝える
香典返しを受け取ったことに対する正式なお礼をする場合は、手紙やはがきで伝えるのが最も丁寧です。
例文(一般的なお礼状)
拝啓
このたびは、ご丁寧なお心遣いをいただきまして、誠にありがとうございました。
故○○様(故人の名前)のご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
また、ご丁寧なお礼状とお品を頂戴し、恐縮しております。
ご遺族の皆様におかれましては、どうか穏やかな日々をお過ごしになられますようお祈り申し上げます。
まずは書中にて御礼申し上げます。
敬具
例文(親しい関係の方向け)
○○さん
このたびは、香典返しをお送りいただき、ありがとうございました。
お気遣いいただき恐縮です。
○○さんやご家族の皆様が、少しでも心安らかに過ごせますようお祈りしております。
また落ち着いたら、お会いしましょう。
電話でお礼を伝える
手紙を送るのが難しい場合は、電話で簡単にお礼を伝えるのも良い方法です。
電話でのお礼の例文
「○○様(喪主の名前)、このたびはお心遣いをいただき、ありがとうございました。」
「お礼状とお品を頂戴しまして、恐縮しております。」
「どうぞお身体を大切にお過ごしください。」
注意点
長々と話さないことがポイントです。弔事に関するやり取りは簡潔に済ませるのがマナーとされています。
メール・LINEでお礼を伝える
最近では、メールやLINEでお礼を伝えるケースも増えています。手紙や電話よりもカジュアルな印象になりますが、相手の負担にならず気軽に感謝を伝えられるというメリットがあります。
例文(メール・LINE用)
○○様
このたびは、香典返しをお送りいただき、ありがとうございました。
お気遣いいただき、心より感謝申し上げます。
○○様もどうかお体を大切にお過ごしくださいませ。
親しい関係であれば、もう少しフランクにしても問題ありません。
カジュアルな例文
○○さん
香典返しありがとうね。
いろいろと大変だったと思いますが、少しでも落ち着ける時間があるといいね。
また近いうちに話せるといいな。
直接会った際にお礼を伝える
香典返しを直接手渡しで受け取った場合は、その場で感謝の言葉を伝えるのがマナーです。
適切なお礼の言葉
「このたびは、お心遣いをいただきましてありがとうございます。」
「お気遣いいただき、恐縮しております。」
「どうかご無理なさらず、お身体を大切になさってください。」
ポイント
「ありがとう」という言葉は、弔事では避ける方が良いとされていますが、親しい関係であれば問題ありません。
香典返し辞退を伝える際のマナー
最近では、「香典返しは不要です」と伝える方も増えています。もし香典返しを辞退したい場合は、事前にその意向を伝えておくことが大切です。
香典返しを辞退する場合の言い方
「お気持ちだけありがたく頂戴いたします。」
「どうかご無理なさらず、お礼などはお気遣いなく。」
「ご遺族の皆様でお使いいただければと思います。」
事前に辞退していても、香典返しが送られてきた場合は、お礼状や電話で感謝の気持ちを伝えるのがマナーです。
おわりに
香典返しのお礼状は、単なる形式的な手紙ではなく、故人を偲んでくださった方々への感謝の気持ちを伝える大切なものです。適切なマナーを守りながら、心のこもった文章を作成することで、受け取る側にも温かい気持ちが伝わります。
本記事では、香典返しのお礼状の基本知識から、書き方のポイント、送付のマナー、簡単に作成する方法まで詳しく解説しました。また、香典返しを受け取った側のお礼の仕方についても触れ、送り手・受け手双方が円滑に対応できるような情報を提供しました。
香典返しのお礼状を準備する際には、
・句読点を使わない・忌み言葉を避ける
・宗教や相手に合わせた適切な表現を使う
・手書き・印刷・メールなど、状況に応じた方法を選ぶ
・送る時期やタイミングを守る
といったポイントを意識すると、より丁寧で心のこもったお礼状になります。
香典返しを通じて、故人を偲び、これまでのご厚情に感謝する気持ちを大切にしましょう。
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
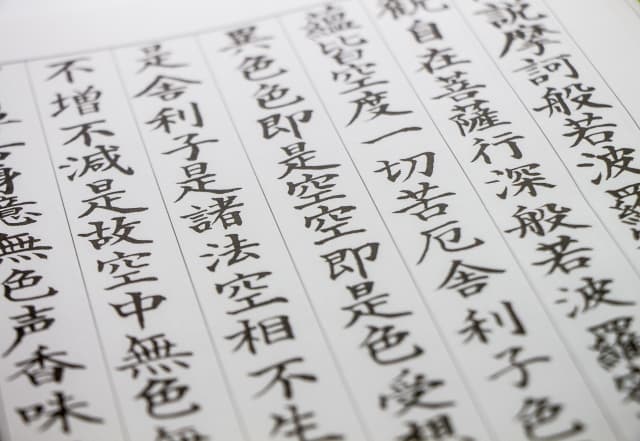
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
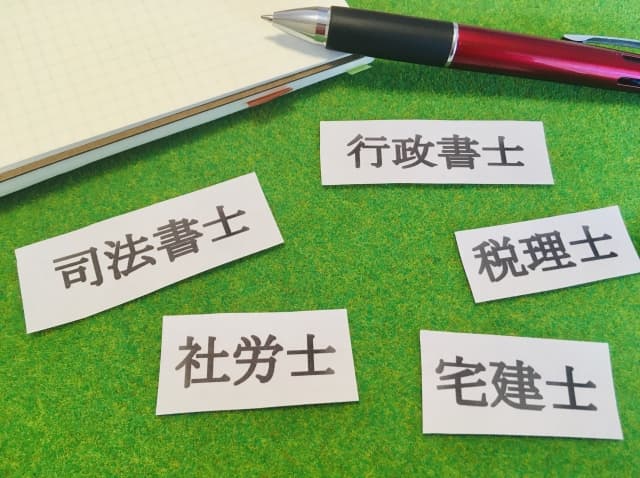
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説


