
清め塩とは?意味や使い方を徹底解説|盛り塩との違いもわかりやすく紹介
公開日: 更新日:
神社の境内や葬儀の後に手渡される小袋の塩、これは「清め塩」と呼ばれ、古来より穢れを祓うために使われてきました。日本人にとってはどこか馴染み深く、しかしその意味や由来、正しい使い方を改めて問われると、明確に答えられないという方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、「清め塩とは何か?」という基本から、その歴史や文化的背景、具体的な使い方、さらには混同されがちな「盛り塩」との違いに至るまで、わかりやすくかつ深く掘り下げて解説します。宗教的な意味合いだけでなく、現代のライフスタイルにどう応用できるのかという観点からもアプローチしていきますので、初めて清め塩に触れる方はもちろん、改めて学び直したい方にも有益な内容となるはずです。
清め塩とは何か?
清め塩の意味
清め塩とは、「塩によって穢れを祓い、場や人を清浄な状態に戻すための道具・行為」を指します。日本において塩は古来より特別な力を持つとされ、神聖な場を整える際や、死に関わる場面において「不浄を払うもの」として扱われてきました。
とくに神道の思想において、「穢れ(けがれ)」という概念は非常に重要です。穢れとは、単なる汚れではなく、人間関係のトラブル、不幸、死など、精神的・霊的な影響を及ぼす負のエネルギーのこと。これを取り除き、元の“清い”状態に戻すことが「清め」です。
その手段として塩が用いられてきた背景には、海から生まれた自然の結晶である塩が、清浄の象徴として認識されていたことが関係しています。日常生活でも、葬儀後に塩を撒く、神棚に塩を供えるなど、塩を使った清めの習慣が各地に根付いています。
清め塩の由来
起源は、日本の神話や古代の宗教的な行動にまで遡ることができます。『古事記』や『日本書紀』には、神が穢れを祓う際に水や塩を用いた描写が見られます。海水は生命の源であり、その結晶である塩には「命を支える力」「浄化する力」があると信じられてきました。
また、古代の相撲において、力士が土俵に塩を撒く「塩まき」も、場を清めるものとして伝わっており、今も大相撲の神事的要素として残っています。これは単なる演出ではなく、神聖な場所に立つ前に身体と心を清める意味が込められているのです。
一方、民間信仰の中でも、塩には魔除けや厄除けの効果があるとされ、玄関や部屋の四隅に撒いたり、塩を入れた袋をお守り代わりに持ち歩く習慣も見られます。このように、清め塩は宗教的背景だけでなく、生活文化としても日本人の心に根付いてきました。
宗教や宗派による清め塩の扱い
清め塩の使用は主に神道に由来しますが、仏教や民間信仰でも取り入れられています。ただし、宗教や宗派によってその位置づけや使用頻度は異なります。
神道では、「祓え(はらえ)」の考えにおいて塩を重要な要素と位置づけており、神事の前後や神前への供え物の一環として塩が使われます。神社での結婚式や地鎮祭、初詣などにおいても清めのために塩が用いられることが多いです。
一方、仏教では宗派によって考え方が分かれます。例えば、浄土真宗では「死を穢れとしない」という教義があるため、葬儀後の塩まきの習慣がない、もしくは避ける傾向にあります。それに対し、曹洞宗や天台宗では、民間習俗と融合した形で清め塩を取り入れることがあります。
また、地方によっても塩の使い方に差が見られます。たとえば東北地方では玄関に塩を盛る習慣が根強く残っていたり、関西では通夜や葬儀後の塩まきを丁寧に行う文化が残っていたりと、その土地ならではの宗教観や生活習慣が反映されています"
清め塩のやり方|正しい手順と注意点
いつ・どこで行うか?
清め塩を使う主な場面は、通夜や葬儀に参列した後、自宅に帰ってくる際です。これは、神道的な考え方に基づき、「死を穢れと捉える」文化から生まれたもので、外から持ち帰った穢れを家に入れないために行うものです。
使用タイミング
・葬儀や通夜の帰宅時(最も一般的)
・火葬場・霊安室・墓地から戻った際
使用場所
・自宅の玄関の外(上がり框の手前)
家の中に入る前に、塩を使って体を清めます。
この清めの行為は、日常空間と非日常空間(死の場)を分けるためのものとされており、清め塩はそのための重要な道具です。
清め塩はどこで手に入る?
【葬儀会場・斎場】
多くの葬儀会場では、参列者が帰宅時に使用できるように、小袋入りの清め塩を配布しています。袋には「清め塩」と印字されているものが多く、そのまま使えるようになっています。
【仏具店・神具店】
正式な用途に使える清め塩が販売されており、葬儀や神棚の供え物などに適したタイプが手に入ります。
【一部の神社】
「御塩(ごえん)」「神塩」などとして授与品になっている場合があります。ただし、参拝目的以外での大量購入は難しい場合があるため、事前に確認が必要です。
【ネット通販】
Amazonや楽天市場などでも「清め塩」「神塩」などの商品名で販売されています。天然塩や国産粗塩を使ったものが多く、袋詰めや器付きのセットなど種類も豊富です。
正しいやり方
葬儀の場から帰宅したときの清め塩の使い方には、ある程度決まった作法があります。
【基本の流れ】
1.玄関の外に立つ(靴を脱ぐ前、敷居をまたぐ前に行う)
2.塩を袋から手に取り出す(少量で可)
3.体の上部から順に塩を振りかける
肩、胸、背中、足元の順が基本
4.足元にも塩を撒く
撒いた塩を軽く一歩踏みしめてから家に入るのが習わし
5.使用後の塩袋は感謝を込めて処分
清めに使った塩は再利用せず、生ゴミにて破棄します
この一連の動作により、葬儀や死にまつわる穢れを玄関先で落とし、家庭内を「清い空間」として保つという考え方が根底にあります。
注意点
清め塩は儀礼的な意味を持つものであるため、以下の点に注意しましょう。
・宗派の違い
浄土真宗など一部の仏教宗派では、「死=穢れ」という概念がなく、清め塩の使用を行いません。
参列先の宗派や地域の風習に応じて判断することが大切です。
・室内での使用は避ける
清め塩は「家の外で使うもの」であり、室内で行うと本来の意味が失われてしまいます。
・塩を踏み忘れない
身体にかけた後、玄関前に撒いた塩を軽く踏みしめてから入るという動作も重要な作法です(踏むことで「場をまたぐ」象徴になります)。
・清め塩は清掃する
使用後の塩はそのまま放置せず、感謝を込めて掃除・処分します。
清め塩の扱いは宗派や地域によって違いがあります。迷ったときは、専門相談窓口をご利用ください。
清め塩についてよくある疑問
清め塩に用いる塩の種類とは?
【基本は「天然塩(粗塩)」】
清め塩には、天然由来の塩(特に粗塩)が最も適しています。これは、塩本来の浄化作用を生かすためです。神道や仏教では、塩は「自然の力を宿すもの」とされ、精製された食塩よりも、ミネラルを豊富に含んだ粗塩の方が「力がある」と考えられています。
【なぜ精製塩は避けるべき?】
市販の精製塩は、加工によってナトリウム成分以外がほとんど除去されているため、浄化の力が弱いとされることがあります。特に神社などで使用される「神塩」や「御塩」は、海水を時間をかけて煮詰めた伝統的な製法で作られており、より清浄とされています。
【おすすめの塩の例】
・海水から作られた国産の天然塩
・神社や仏具店で販売されている「清め塩」や「神塩」
・自宅で塩を素焼きにすることで、穢れを祓う用途にも適する
清め塩は自宅で用意できる?
はい、特別な塩を購入しなくても、自宅で簡単に清め塩を用意できます。
【自宅での清め塩の作り方】
1.粗塩を小皿に分けて用意する
2.新聞紙や和紙に包んで「塩袋」として持ち歩けるようにする
3.清潔な容器に入れて玄関などに備える
さらに清めの力を強めたい場合は、以下の方法もあります
・塩をフライパンで軽く炒る(素焼き):不純物を飛ばし、より清めの力を強めるという考え方もあります。
・日本酒を少量加える:塩と酒の組み合わせは、神道において「祓いの基本」とされており、さらに清浄な性質が加わります。
清め塩の処分方法は?
使い終えた清め塩の処分には、丁寧な心構えが大切です。祓い清めの行為が終わった後の塩は、「役割を果たした道具」として感謝の気持ちを持って処理しましょう。
【一般的な処分方法】
・生ごみとして紙に包んで捨てる
→ この際「ありがとうございました」など、感謝の一言を心で唱えるとよいとされています。
・水で流す(シンクや川など)
→ 塩は水に溶けるため、自然に還すという意味で水に流すという方法も一部に見られます。ただし、塩分が環境に与える影響を考慮して少量にとどめましょう。
【やってはいけないこと】
・清め塩をそのまま長期間放置する(湿気や悪臭の原因に)
・清めに使った塩を再利用する(役割を終えたものには再利用の力がないとされる)
盛り塩との違いは?
盛り塩とは何か?
盛り塩とは、小皿の上に山型や円錐形に盛った塩を室内や玄関、店舗の入口などに設置することで、空間を整え、良い運気を招くとされる伝統的な風習です。主に風水的な観点や民間信仰に基づいて用いられます。
この風習のルーツは、平安時代の宮中に遡るといわれています。当時、牛車を引く牛が道端の塩に誘われて停まる様子から、「塩を盛っておくと高貴な人物(良い客)が訪れる」と信じられたのが起源とされます。やがてこの風習は商家や旅館、飲食店に広まり、「集客の願掛け」や「繁盛祈願」として定着しました。
現代では、風水との結びつきが強まり、「玄関に盛り塩を置くと良い気が入る」「部屋の四隅に盛ると空間が浄化される」といった使い方が一般的です。特に気の入口とされる玄関や、水回りなど邪気が溜まりやすいとされる場所に設置する例が多く見られます。
清め塩と盛り塩の違い
一見すると似たような行為に見える清め塩と盛り塩ですが、目的・使い方・宗教的背景のすべてにおいて異なります。
項目 | 清め塩 | 盛り塩 |
|---|---|---|
主な目的 | 穢れを祓う | 福を招く・邪気を防ぐ |
使用場面 | 葬儀後の帰宅時など | 商売繁盛、風水対策など |
使用場所 | 玄関の外、身体 | 店舗の入口、部屋の四隅、玄関内 |
方法 | 撒いたり身体に振りかける | 皿に盛って置く |
宗教的背景 | 神道の「祓え」思想 | 民間信仰・風水の影響 |
清め塩は一時的な使用で、使った後はすぐに処分します。一方、盛り塩は一定期間設置し、定期的に取り換えるのが一般的です。形状にも違いがあり、盛り塩は視覚的な整え方も重視されるため、綺麗な山型や円錐形が好まれます。
清め塩の主眼は「祓うこと」
清め塩は、神道的な「祓え」の思想に基づき、「死」「病」「災い」などを「穢れ(けがれ)」と見なし、それを祓い清めるために使われます。特に葬儀の後、玄関に入る前に身体に塩を振るのが典型的な用法です。
これは、「非日常(死の場)」から「日常(家庭)」に戻るための精神的・宗教的な通過儀礼の一つであり、一度限りの使用が原則です。
盛り塩の目的は「招くこと」
一方で盛り塩は、「場のエネルギーを整え、良い運気を呼び込む」という招福・開運を目的とした方法です。盛り塩の原型は、平安時代の宮中儀礼に由来すると言われていますが、江戸時代以降は特に商家や旅館などで「お客様を呼び込むための縁起担ぎ」として広まりました。
現代では、風水の影響もあって「玄関に盛り塩を置くと良い気が入ってくる」「悪い気をブロックする」という目的で家庭でも広く使われています。見た目を整えるために円錐形にしたり、素焼きの器を使ったりするのが特徴です。
使い分けのポイント
・穢れを祓いたいとき → 清め塩
葬儀や病院の帰りなど、「外から悪いものを持ち帰ったかもしれない」と感じたときに使用。
・運気を上げたい・場を整えたいとき → 盛り塩
新しい始まり、ビジネスの繁盛、家庭運アップなど、「良い気を招く」目的に。
注意すべき点
・清め塩と盛り塩を混同して使わない
たとえば、葬儀後に盛り塩を使うのは本来の意味から逸脱してしまいます。
・どちらも「塩を通して自分と空間に意識を向ける」という精神性が重要
形式だけでなく、意図や心構えをもって行うことが大切です。
まとめ
清め塩とは、古来より日本で受け継がれてきた「穢れを祓い、空間や身体を清浄に戻す」ための習慣です。特に葬儀や通夜といった“死”に関わる場面で使われることが多く、神道における「祓え」の考え方に基づいています。玄関の外で塩を使うことで、外からの穢れを家庭に持ち込まないようにするこの行為は、日常と非日常の境界を意識し、気持ちを切り替えるための大切な営みです。
本記事では、清め塩の意味や由来から始まり、正しい使い方や注意点、そしてよくある疑問までを解説しました。さらに、盛り塩との違いについても掘り下げ、それぞれが持つ役割や目的を明確にしました。
大切なのは、単に塩を使うという行動だけではなく、その背景にある意味を理解し、自分の意図を持って使うことです。清め塩は、必要な場面で心身や空間を整えるために一時的に用いるものであり、盛り塩は空間の気を良い状態に保ち、良い縁を呼び込むために日常的に設置されるものです。
この違いを理解し、目的に合わせて使い分けることで、私たちの暮らしにも日本人の知恵や精神性が自然に息づいていくことでしょう。
清め塩や盛り塩に関する具体的な疑問や、ご家庭の事情に合わせた使い方を相談したい場合は、お気軽に相談窓口へ。
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
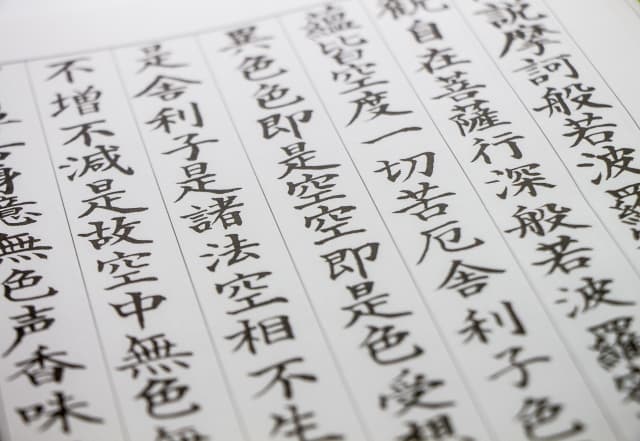
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
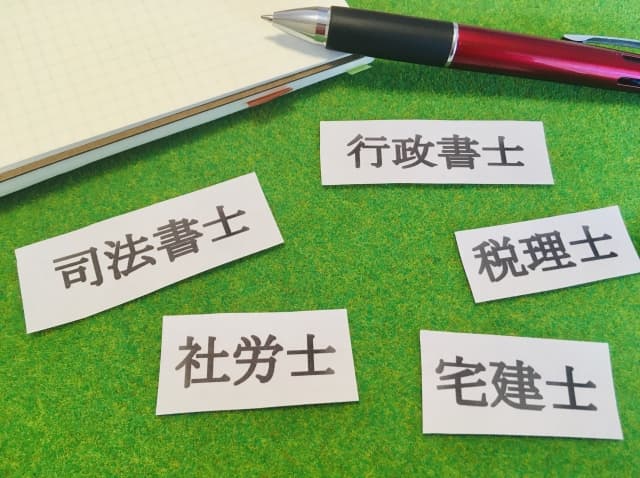
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説

