
家族葬の費用相場から節約のコツまで|知っておきたいポイントと注意点
公開日: 更新日:
「静かに、心のこもったお別れをしたい」という想いを反映できる家族葬は、多くの人に選ばれる葬儀形式です。しかし、家族葬を選ぶ際には、費用や手続きのポイントを事前に知っておくことが重要です。この記事では、家族葬の基本知識から費用の相場、節約方法、注意点、そして納得のいく葬儀を行うための具体的なステップを詳しく解説します。
家族葬とは?一般葬との違い
家族葬の定義と背景
家族葬は、家族やごく親しい友人のみで行う小規模な葬儀のことです。従来の一般葬が、多くの参列者を迎えて行う儀式的な性質を持つのに対し、家族葬はプライベートな空間で、故人との最後の時間を過ごすことに重点を置きます。
家族葬という形式は、20世紀末頃から日本で広がり始めました。「静かにお別れをしたい」「形式にとらわれない自由な葬儀を行いたい」というニーズの高まりが背景にあります。また、コロナ禍の影響で「人との接触を極力避けたい」という安全面のニーズや、「限られた近親者だけで静かに送りたい」という心理的なニーズの高まりも背景にあります。
他の葬祭方法との違い
家族葬は、さまざまな葬祭方法の中でも独自の特徴を持ちます。以下に主要な葬祭方法との違いを比較しました。
火葬/直葬 | 家族葬 | 一般葬 | 社葬・合同葬 | |
|---|---|---|---|---|
参列者 | 家族のみ(数名) | 家族・親しい友人のみ(数名~20名程度) | 知人・仕事関係者を含む数十~数百名 | 社員・取引先・関係者を含む大規模な人数 |
費用 | 安価(10万~30万円) | 中程度(50万~150万円) | 高額(150万~300万円) | 非常に高額(300万~1000万円以上) |
主な特徴 | 火葬のみを行い、儀式を省略 | 静かで落ち着いた雰囲気で、個別性が高い | 伝統的かつ厳粛な儀式を重視 | 組織・団体を代表して行う公式性が高い葬儀 |
期間 | 数時間(火葬のみ) | 通夜・葬儀・火葬で1~2日程度 | 2~3日程度 | 2~3日以上(規模により変動) |
料金の差は参列者の人数によって大きく変化することが多いです。参列者の人数が増えることで返礼品や、食事の数を人数に応じて増えていくため費用が高くなってしまいがちです。
家族葬が選ばれる理由
家族葬が多くの人に選ばれる背景には、以下のような理由があります。
1.少人数で行えるため、ゆっくりとお別れができる
多くの人に気を遣うことなく、故人との最後の時間をじっくり過ごせます。
2.プライバシーを確保しやすい
家族だけの空間で、外部の目を気にせず静かにお別れをすることが可能です。
3.費用を抑えられる可能性が高い
一般葬よりも参列者が少ないため、飲食費や返礼品の負担が減り、コストを下げやすくなります。
家族葬の費用相場
家族葬の平均費用
家族葬の費用は全国平均で50万~150万円ほどと言われています。地域差や葬儀規模、選ぶプランによって費用は変動します。
1. 式場使用料
式を行う場所の借用料で、式場の規模や地域により費用が変わります。公営の斎場は組織市・組織区住民(斎場を運営している市・区に住む住民)でない場合、組織市・組織区住民の2~3倍の料金がかかります。民営の式場を使う場合、式場使用料が葬儀一式費用に含まれている場合が多いです。
相場:5万~30万円
2. 祭壇費用
祭壇の種類や装飾の豪華さに応じて費用が異なります。祭壇の規模、使用する花の種類や量、装飾品の種類の種類で費用が変わります。
相場:10万~50万円
3. 火葬料
公営の火葬場を利用すると、費用が抑えられる場合があります。組織市・組織区住民であった場合、火葬場の使用料が無料になる場合があります。
相場:無料~10万円
4. 遺体管理費用
安置料やドライアイス代など、火葬までの間の遺体保存費用が含まれます。
相場:1日あたり5000円~2万円(安置料)+1万~2万円(ドライアイス代)
5. 飲食費用
通夜ぶるまいや精進落としの飲食代です。人数に比例して費用が変動します。
相場:1人あたり3000円~5000円
6. 返礼品費用
参列者に配るお礼の品物の費用です。お茶やハンドタオルからカタログギフトまで様々です。
相場:1個あたり500円~3000円
火葬までの期間が長くなる場合の管理費用
火葬場の予約が取れず火葬までの日数が延びる場合、多くの場合その間の遺体管理費用が増加します。以下の費用がかさむことに注意しましょう。
安置施設の使用料
1日あたり5000円~2万円程度が相場です。長期間利用する場合、累積する費用が負担となることもあります。
ドライアイス代
遺体保存のためのドライアイス代は1回1万~2万円程度が必要で、数日分積み重なると費用が増えます。
送費用
自宅から式場、火葬場への移動が複数回にわたる場合、追加費用がかかる場合があります。
家族葬のメリット
家族葬は、シンプルでプライベートな空間を確保できる点で人気ですが、選ぶ前にそのメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
1. 静かで穏やかな雰囲気でお別れができる
一般葬のように多くの人が参列しないため、慌ただしさがありません。
そのため、家族や親しい友人だけで穏やかな時間を過ごせます。
また、葬儀後に写真や動画を通じて、心静かに故人を偲ぶひとときを持つ方も多いです。
2. 準備が比較的簡単
参列者が少ないため、準備する項目が減ります。そのため招待状や席次表の準備が不要なケースが多いです。また、短期間でスムーズに進めやすく、遺族への負担が軽減されます。
3. 費用を抑えられる可能性が高い
家族葬は参列者が少なく、飲食費や返礼品などの負担が減ります。そのため豪華な装飾や演出を控えることもでき、不要なオプションをカットすることで費用を節約可能です。
家族葬のデメリット
1. 親戚や知人への対応が必要になる場合がある
家族葬に呼ばなかった親戚や友人が、後日弔問に訪れることがあります。そのため予想以上に弔問者が増えると、その対応に時間や手間がかかる場合があります。また、葬儀後に親戚間での意見の相違が生じる可能性も考慮が必要です。
2. 火葬までの期間が長くなると追加費用がかかる
火葬場の予約が混み合っている場合、火葬までの期間が延びることがあります。その間の遺体管理費用(安置料やドライアイス代)が追加されることに注意しましょう。
3. 故人を偲ぶ場が少なくなる場合がある
参列者を限定するため、多くの友人や知人が故人とお別れできないことがあります。これにより、後日「直接参列したかった」との声が寄せられることもあります。
家族葬の費用を安く抑える方法
高くなってしまいがちな家族葬の費用を抑えるためには以下の4点が有効です。
1.複数の葬儀社に見積もりを依頼
複数社からの見積もりを比較し、価格やサービス内容が理想に合っているプランを選びましょう。
2.不要なオプションを削る
不要な装飾や高価な返礼品などを削ることで、コストを削減します。
3.自宅や公共施設を活用
自宅葬や地域の公共施設を利用することで、式場使用料を削減できます。
4.補助金を活用
自治体の葬祭費補助金を申請することで、数万円の助成を受けられる場合があります。
葬儀費用の支払い方法
葬儀費用は家族葬の中でも重要なポイントです。費用をスムーズに支払い、後々のトラブルを防ぐために、以下の支払い方法と注意点を押さえておきましょう。
1.現金払い
小規模の葬儀社や地域密着型の葬儀社では、現金払いが使われます。ただ、都心や大手の葬儀会社であっても、火葬料金やお布施など現金が必要な場合も多くあるので、あらかじめ葬儀社やお坊さんへ確認しておくと良いでしょう。
2.銀行振込
葬儀費用の支払いを銀行振込で行うこともできます。葬儀社から発行された請求書や見積書に記載された口座に振り込む形式です。
3.クレジットカード払い
最近では、クレジットカードで葬儀費用を支払える葬儀社も増えています。一括払いだけでなく、分割払いやリボ払いが利用できるため、経済的な負担を軽減できます。
4.分割払い・ローン
一部の葬儀社では、分割払いやローンのサービスを提供しています。まとまった資金を用意するのが難しい場合に有効です。
まとめ
家族葬は、静かで心のこもった葬儀を実現できる一方、費用や準備に関する課題も存在します。費用の内訳や抑える方法を理解し、事前に信頼できる葬儀社と相談することで、満足のいくお別れを実現することができます。
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
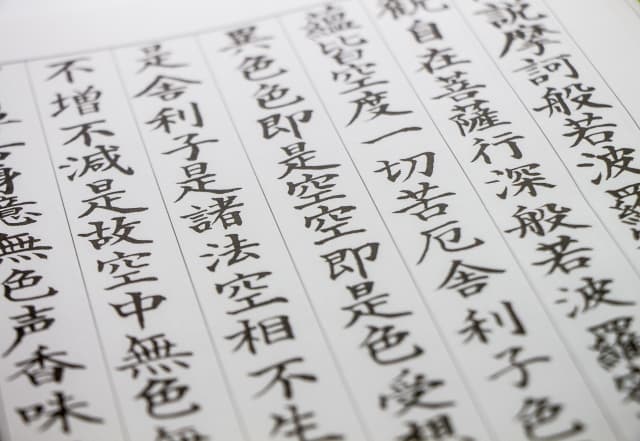
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
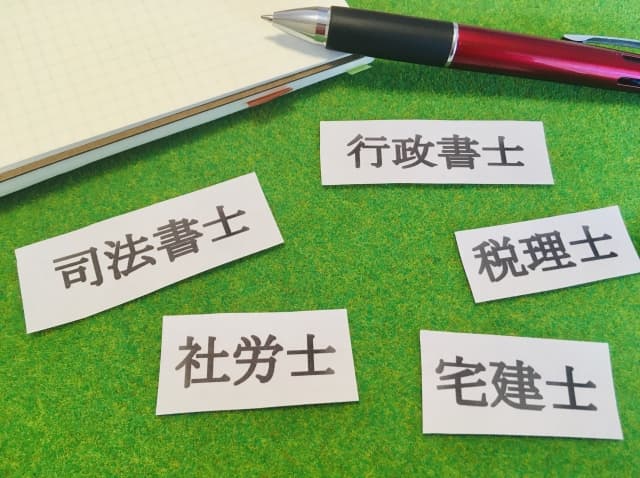
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説

